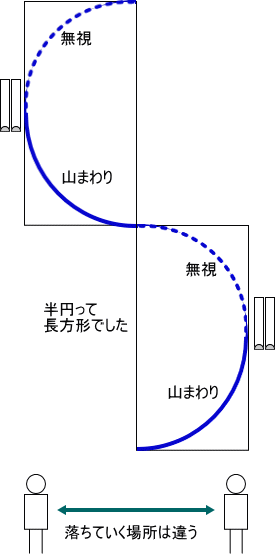|
(�͂��߂Ɂj ���z�͎��R�ł���I �����T�O���������Ȃ�����N�����߂��́H�H �u���ƗE�C�v |
||||||||||||||||||||||||
����Ƃ́H ���i����ɂ͒��������܂���B�S�����i���Ă��ǂ��̂ł��B �u���蓖���ɂ����Đ搶�ɂȂ��Ă���l�ɔF����n�������v���Ǝ��͎v���̂ł��B �u���v�Ƃ��ėՂ�ł��܂��H�H�i�����痈�N�����Ă��������ƂȂ�̂ł��傤���E�E�E�j �ڕW�ݒ�H �e��ڂV�T�_�����i�ł��B �����ŖڕW���u�V�T�_�v�ɐݒ肵�Ă��܂��H�H �ْ����Ă��܂������Ȃ��āA������V�S�_�Ƃ��V�R�_�Ƃ����o�Ă��܂��̂ł��ˁB �������Ă������́u�e��ځ{�T�_�ȏ�v����邱�Ƃ�ڕW�Ɏ��g�݂܂����B��������Ώ������炢���s���Ă��]�T�ō��i�_���o��͂��ł��B�ǂ���������������炻�������_���o�邩�ƃC���[�W�ł���Ηǂ��̂ł����E�E�E�B �ł��{���ɂ�肽�����Ƃ��Ă���ł���ˁB �V�T�_��ڕW�ɂ��邱�Ƃ͊Ԉ���Ă��܂��B�W�O�_�ȏ��ڕW�ɂ��Ȃ���A�Ӗ�������܂���B �P���̑O���Ƃ��Ċ��邱�Ƃ��ł��܂����H |
||||||||||||||||||||||||
�ȉ��A�����̃q���g�̂���ł��B �P�j�R�܂�� �@���ΖʂŁA���t�H�[�����C���i���j�Ɍ�����������R�܂��̕����̂݁A��������Ɗ���B ���̕����͖����B�E�^�[���̖c��݂̒[����R�܂��A���^�[���̖c��݂̒[����R�܂��B �Ƃɂ����A�R�܂��݂̂������芊�邱�Ƃ��l���܂��B �����猩���ꍇ�A���̕������������肵�Ă���ƈ����]�����o���Â炢�B�����܂������Ă��܂��B
|
||||||||||||||||||||||||
�Q�j�R�u �R�u���Ăǂ�����Ăł��܂����H�N�����X�R�b�v�ŎR�����̂ł��傤���H �Ⴂ�܂���ˁB�X�L�[���[����]���邱�ƂŒ���Ă������Ƃłł���̂ł���ˁB �����Ă��鎞�ɁA�R�u������č~���Ƃ������Y���Łi�u�R�v�Ɗ����āj�����Ă��܂��H ������^�[���ƃ^�[���̂Ȃ��ڂŁu�҂v�Ƃ������Ԃ��ł��Ă��܂��A���ꂪ�r��Ă��܂��܂��B �X�^�[�g���R�܂�肩��X�^�[�g���Ă��܂���ˁB�R�܂��J�܂���r��Ȃ������āA�x�e�B ����͍u�K���ɂ���������Ƃ���ł��B���n������K���Ă��������B �����āA�R�u�ɓ���܂��B �R�u�̎R�̒��_���Ȃ����ʂ��l���܂��B�i�v�`�v�`�V�[�g�݂����Ɂj ���ꂪ���Ƃ��Ƃ̎Γx�ł��B�^�[���̊�͔��t�H�[�����C���Ɍ��������B �����āA�R�u���u�~��Č��ɖ߂�v�i�������ďオ��j�i�u�J�v�Ɗ����āj�Ƃ������Y�����l���܂��B ����Ƃǂ��ł��傤���H ��̃o�����X�ɖ߂��Ă��邱�Ƃł��傤�B ������o�����X������Ȃ��̂ł��B |
||||||||||||||||||||||||
�_�������2004�N���p���͂����炩�� 2006�N���p���͂����炩�� |
||||||||||||||||||||||||
2006.3.4�`3.5 �@�v�X�Ƀv���C�x�[�g�̎��Ԃ���ꂽ�̂ŁA���Ԃ����Ɛ����ŗ��K���Ă��܂����B �����̕��X�����K���Ă��܂����ˁB���͍���������g���[�j���O���ł��B�X�s�[�h���o���Ƒ̂��t���[�Y���Ă��܂��܂��B �i�s���S�R�Ăŏ��������Ă��������������ƁE�E�E�j �Z�p���ɂ́u�Z�F�킴�v�Ɓu�p�F����v�̗��ւ��K�v�Ǝv���܂��B �Z�F����̂������A���Y���ƃ^�C�~���O�A���Ă���҂ɑi���銴���E�E�E �p�F���Z�����鎞�̊����̈ӎ��A�Z�����������邽�߂̍��E�E�E �p���w�ڂ��Ƃ���l�͏��Ȃ��Ȃ�܂����ˁB��l�̃m�E�n�E�v������̂͂��������Ȃ����Ƃł��B�V�������_��l�����͎^���ł����A�ߋ���ے肷�邱�Ƃ͋����܂���B �X�L�[���o�ꂵ�Ă���S�R�ς���Ă��Ȃ����ƁA �P�j�Ζʂ̏ォ�牺�Ɋ��邱�Ɓi��邱�ƂɌ����ɂȂ��Ă��܂��H���������ł��B�j �Q�j�E�^�[���̎��ɍ��^�[�������邱�Ɓi�ǂ̕����ɐ�ւ��̃��C��������Ă����܂����H�j �Ζʏ���~�^�����Ȃ��痎�����Ă������Ɓ����R�̒n�`�ɑΉ�����p�A�|�W�V���j���O�A�Ҋ߂̂Ђ˂�^���E�E�E���ꂪ�o���Ă��Ȃ��l�������B������g���Z�ƂƂ��ɁA����𑀂�l�̃o�����X�́A��������A�߁E�ؓ��̏_���������E�E�E�A�l�����ƌ����Ă��\��Ȃ��B�^���������ʂƂ��đS�g�̃V���G�b�g���ǂ������邩�H�Ƃ��������Ƃ��]���ɂȂ�̂́A�����̂������Ȃ��̂ɁE�E�E�B ���T���͑S�����i�����F�肵�Ă���܂��B�f�G�Ȑ搶�ɂȂ��Ă��������ˁE�E�E�B  �� Click here |
||||||||||||||||||||||||
2006.3.29 ���T���A���g���ɂ�  ����́A�g���m�I�����s�b�N�ɏo�ꂷ��I��̊����������T�|�[�g�������Ƃ̔M���z������i�V���i���f�����X�g���[�^�[�����������グ�����o�[�o���h�B ����́A�g���m�I�����s�b�N�ɏo�ꂷ��I��̊����������T�|�[�g�������Ƃ̔M���z������i�V���i���f�����X�g���[�^�[�����������グ�����o�[�o���h�B<�@�Q�l�܂ł�SAJ�T�C�g�͂����炩�� >  �Z�p�I�����̒��ɐ�Ă��܂����u�����v�Ɓv����̂��́B �{�l�H���@�u�����A��Ă��܂����B�B�B�ǂ����悤�B�B�B�v �߂���߂���w�R���f���܂����Ƃ̂��ƁB �����̊C�삭��u����~�T���K�Ɠ����ŁA�肢�����Ȃ���I�����Ƃ��Ȃ���I�B�B�B�v ����ȗ�܂�������A�����I����̌��ʂ͂Q�ʂƂP�_���B �P�Ɂu�`�����s�I���ɂȂ肽���v�̂ł͂Ȃ��AALPINE SKI �̏����E�E�E�A���Z����b���Ȃ��A�A���y���X�L�[�̗��_�͈ꏏ�̂͂��E�E�E�A�����v���Ă������Ɠ����l���������̂ł��ˁB���̊���𐄂��i�߂邽�߂̃`�����s�I���̏̍��E�E�E�B �ꏊ�����ɂȂ�Ƃ���ɁA�h���}������̂ł��ˁB�B�B�Ƃ��Ă��S�����܂�������ł����B��t�b���āA�{�g������ɂȂ����̂͌����܂ł�����܂���B�B�B
���������P���撣���Ă݂悤���ȁB�B�B |
||||||||||||||||||||||||
2006.4.22 �u�ꍂ���F�̓��X�L�[�� �Z�p���L�u�ɂ��n�ӈ���g���[�j���O�ɎQ�����Ă��܂����B  �����̎ʐ^�ƃr�f�I�̓v���J�����}���̗�؍_����ɎB���Ă��������܂����B ���肪�Ƃ��������܂����B�i�\���Ɏg�p�����Ă��������܂����B�j |
||||||||||||||||||||||||
���y�[�W�̐擪�� ���ŐV�̋L���� |
2006.5.6 �V����X�L�[��`�쑽���� �i�R�u�̒��������Ă����������l����́A����ς肤�܂������E�E�E�B�j
|
|||||||||||||||||||||||
2006.5.7 �@�F�X�ȕ��X����A�h�o�C�X�����������A�R����{�܂Ńt���[�Y���Ă������o�����炬�A���܂łɂȂ����o���m�F�ł��܂����B���܂��Ă���DVD�Ȃǂ�����@�����A�u�Â̕��p�v�Ɋւ�����̂͌��݂̃X�|�[�c�ɂ����p�ł�����̂Ɗ����Ă��܂��B �����ŁA�X�L�[�̏ꍇ�A�E�^�[���̎��ɍ��^�[�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�̂̈ʒu�����ւ���̂ł����A�����ŃX�L�[���[�������v���Ă��邩�i�C���[�W���Ă��邩�j���厖���Ǝv���̂ł��B �}�ɂ��Ă݂܂����B�i�Ƃ肠�����A���ʏ�ōl���܂��傤�B�j 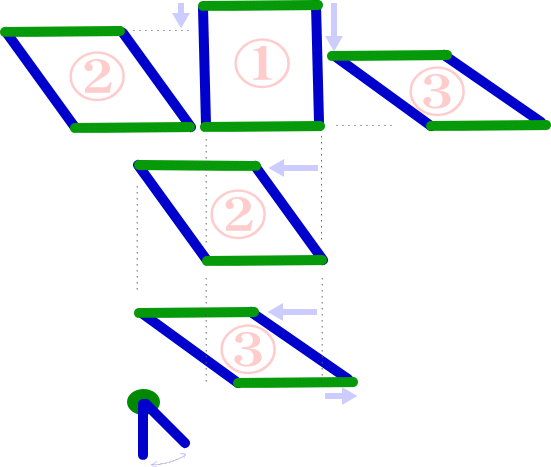 �P �� �Q�@�֓����Ƃ��A�������Œ肵����Ԃō�������ֈړ�����Ƃ��܂��B �P �� �R�@�֓����Ƃ��A��L�̍�������ֈړ����铮���{��������ֈړ�����Ƃ��܂��B ��r���Ă݂�ƁA�u�P �� �R�v�֓����������A���Z���Ԃɑ傫���ړ��ł��邱�Ƃ��킩��܂��B �������̃X�L�[���[���o�Ō����ƁA�u�����i���j���O���ɃX�C���O����悤�v���u�����̌Ҋ߂̐^���Ɉʒu����������A�O���̌Ҋ߂̐^���ֈړ�������悤�v�Ȋ����ł��B ���̏ꍇ�A���ȍ��^�[���͖��ӎ��Łu�P �� �R�v�̓��������Ă��܂����B�s���ӂȉE�^�[���́u�P �� �Q�v�̓��������ăt���[�Y���Ă����݂����ł��B���̂��ߍ��E�̕s�ϓ�������Ă��܂����B���̓����̃X�C���O���o���ӎ����邱�ƂŁA�^�[���|�W�V���������P����Ă����݂����ł��B �i�^�[���O���ɁA�������`���A���ꂪ����Č�����悤�ł��B�j ���ƂQ�`�R��A�������⌎�R�ŁA�Q�O�O�V�V�[�Y���d�l�Ɏd�グ�Ă������Ǝv���Ă��܂��B �i�N���r�f�I�B�e��`���Ă���Ȃ����ȁH�H�j |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.12 �X�L�[�̊�{�̓V���e���^�[���ł���I �@�ŋ߃A���y���X�L�[�R�[�`�̃u���O�Ȃǂ����Ă��܂��ƁA�W���j�A�I�肪�u�Y���i�^�[���O���j�̃X�L�[���o���Ȃ��v�Ƃ̒Q���𑽂��݂����܂��BGW�Ɍ�������DVD�̈�ɍ��X�ؖ�����̂Q�O�O�R�N�V�[�Y���I�t�̃L�����v�摜������܂����B�u���[���h�J�b�v�ɏo�Ă���I��ł��̂���ɒJ�Ɍ����āA�Y���̑�������ł�����芊����K���R���܂��B�܂��Ă��{��g�ɒ����鎞���̃W���j�A�̑I�肱���A�������K���Ă��������B�v�Ƃ���������̃R�����g�ƌ��{�̊���ł����B �@����i�����Ă��A�P���ɁA�R����J�ցi�X�^�[�g����S�[���܂Łj�����ړ����邱�Ƃ��o�����l����肾�Ǝv���̂ł��B���������邽�߂ɂ͑̂͏�ɒJ�������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ł��B�X�s�[�h�������ƃt���[�Y���Ă��܂��̂����ʂł�����A�������Ƃ����X�s�[�h������K�����ł��ˁB ������V���e���^�[���ł���I ��ւ��ŊO�X�L�[�����܂��i�̂��痣���܂��j����A�O�X�L�[�����_�ɂ����^�[���|�W�V������������A���z�I�ɂ��܂�܂���ˁI�p�������^�[���̏ꍇ�A�̂��ړ����ē����|�W�V�����ɂ͂܂�̂�����̂ł��ˁB�ŋ߃V���e���^�[�������Ă���l�͌������܂���B���i����̎�ڂɁu�s���n�ł̃V���e���^�[���v������܂��B�v���C�Y����ł́u�s���n�ł̃p�������^�[���v�ɂȂ�܂��B���w�����邽�߂ɂ��遁���K���邽�߂ɂ��遁�X�s�[�h�̎����������ē����v�f���g���[�j���O������čl����̂́A�������i�H�j�E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.13 �������ێR�X�L�[��ցiau�̓d�b�͌��O�ł��B�ǂ��ɂ����Ă�KDDI����I�j
�i�Q�j�y�������ȃI�����W�o���_�i�`�[���B�I�t��̂悤�ɔq�����܂����B �i�R�j�Ԃȕ��q���b�e���ł��R�u�͂���Ȃɑ傫������܂���ł����B ��P���t�g�͉c�ƏI���܂Ő��n�̃g���[�j���O���ł��܂����B�i��͂܂��܂�����܂��B�j �i�S�j���P�̒�������������E�^�[���B �r�f�I���R�}����Ō��Ă��܂��ƁA��ւ��Ɂu���v�Əo�܂����B�i���ꂩ����P�Ɏ��g�݂ł��ˁI�͂����ĂQ�O�O�V�V�[�Y���܂łɊԂɍ������E�E�E�B�j �����͂Q�T�ǂ�K.M����ɎB�e���Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.15 �F�쌫���Y ���������ɉ�����̓��̉w�ł��͂�i�����Z�b�g�j��H�ׂȂ���A�G�����y���y���߂����Ă�����A�F�쌫���Y����̃C���^�r���[�L��������܂����B �i�L�ҁj�P�O�N����X�L�[������Ă���Ǝv���܂����H �i���j�u����Ă������ł��ˁA���Z�́B���`�x�[�V������������������ł����ǂˁB ����Ɩl�̓A���y���ł����A��b�X�L�[�A����͓��{�Ɠ��̃V�X�e�����Ǝv����ł����ǁA�l������Ă���ԂɁA�Ⴆ�ΒʎZ�V���[�Y�ɂ��đS����]�킷��Ƃ��ɂȂ��āA�����ƃ��W���[�ɂ��āA�����Ƃ��Ċ�b�X�L�[����ĂĂ���������Ȃ��čl���Ă��܂��B�v �V�����Ǝ� �V���̐������CARREL�i�L�������j2006�N5�����@VOL.145 p41��� �����A���N�O���玄�������Ă��邱�ƂƓ�������Ȃ��ł����E�E�E�B �iSAT�̃V�j�A�Z�p�I�̃V���[�Y���͎����ł��܂������ǁE�E�E�B�j �Ƃ肠�����A�V�����̉��z�G���A�̃X�L�[��]��V���[�Y�������������ȁE�E�E�B �F�쌫���Y�̃u���O�@http://ameblo.jp/kentaro1up/ �`�[���A���r���b�N�X�V���@http://www.team-albirex.com/ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.16 �h�p�T�v���i�H�j �����ɂQ�{�̃}�b�`�_������܂��B���̂Q�{���E�E�E�B 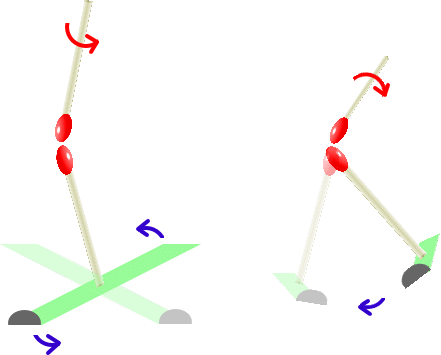 �i���̂Q�{�ŋr���C���[�W����Ȃ�āA�قƂ�ǃr���[�L�ł��ˁE�E�E�B�j ���āA �i�P�j�d�S�ʒu���������Ă����đ�ڕ���P��ƁA�u�Ђ�����Ԃ����|�g���{�v���悤�ȓ����ɂȂ�܂��B������肵���X�s�[�h�Ŋ���Ƃ��Ɏg�������ł��ˁB �i�Q�j�d�S�ʒu��Ⴍ���Ă����đ�ڕ���P��ƁA�u�����X�C���O�v����悤�ȓ����ɂȂ�܂��B�n�C�X�s�[�h�Ŋ���Ƃ��Ɏg�������ł��ˁB ������ڕ���P�铮���ł��A�d�S�ʒu���Ⴄ�ƌ��ʂ�����Ă��܂��B ���Ȃ��͂ǂ̂��炢�̃X�s�[�h�łǂ������g���܂��H�H |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.20 �������ێR�X�L�[���
���X�ؖ�����̒ᑬ�g���[�j���O��V���e���^�[���i�V���e���N���X�`���j�A�H�j����K�B �n�C�X�s�[�h�ł̑ǎ��|�W�V���j���O�̃g���[�j���O�B �n�C�X�s�[�h�ł̐�ւ��̃g���[�j���O�B Y�������V�[�Y���ō��̊��G�Ƒ喞���I�i�����P�R�Ŋ���܂��傤�Ƃ������ƂɁE�E�E�B�j �������͗��T�ʼnc�ƏI���Ȃ̂ŁA���T�����s�����Ⴂ�܂��B �������[�����@�i�N�S�E�T��͖K��܂��j �V���������s�����Q�@0257-92-5405 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.21 ����Ȃ��L���̕��Q ������Ȃ��遁�u�[�c�̃^���O�i�x���j�����ĂđO�������͂�������A�Ƒ��Ȃ���܂��B 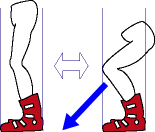 �̂���u��ʂ���߂��߂��瓮�����v�ƌ����Ă������̂ł��B���̐M���ł���u���z�͎��R�v�Ƃ������ƂŁA�������Ă݂܂��ƁA���̓����͎��̎��Ɏg�������ł��B �i�P�j�X�s�[�h������Ȃɏo�Ă��Ȃ����A �i�Q�j�X�s�[�h���łȂ��悤�ɒ������鎞�A �i�R�j�������̃o�����X��肪���܂��ł��Ȃ����E�����X�L�[���[���r�̊e�߂��Ȃ��邱�ƂŌҊ߂̉����U�����āA�p�t���̋����g�ɂ���w�K�����Ă��鎞�A �ȂǁE�E�i�����Đ̂̂��Ƃ�ے�I�ɑ����Ă͂����Ȃ��Ǝv���̂ł��B�j ���āA�n�C�X�s�[�h�̏ł͂ǂ��ł��傤���H �ǂ���������̂��A�^�[���O���̑�����Ȃ��߂��邱�ƂŁA ���@�X�L�[�̑O���ɕK�v�ȏ�ɉd��������܂� ���@�X�L�[�Ƀu���[�L��������܂��i�������܂��j ���@�e�[�����y���Ȃ�܂��i�X�L�[���u���܂��j �����āA���ۂƂ��ẮA �i�P�j�O�X�L�[���x��܂�����A���X�L�[�̊������ɕ����ė��X�L�[�̐悪�J���܂��B �i�Q�j�^�[���̌㔼�ŊO���������Ă��ڂ�ɂȂ�����A�X�L�[���g�ł����肷��悤�ȏǏł܂��B �X���[�X�Ɋ��������ǂ��^�[�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��ˁB���v���ƌ��ʂ�����Ă��܂��B ���������A�X�e���}���N�I�肪��������̍��̃X�L�[�G���ɁA�u�g�b�v�I��ɂ͑��L�т������p����������E�E�E�B�v�ƒN���̎�ދL���ɏ����Ă��������Ƃ��v���o���܂����B�i�̂������ς��Ȃ����E�E�E�B�j �T�X�y���V�����V�X�e�����A�u�o�l���v����u�E�B�b�V���{�[�����v�ɐi������悤�Ȋ����i�H�j ���S�n���ǂ��Ȃ�̂ł��傤�ˁB ���āA����Ȃ��Ȃ��Ŋ����Ă݂܂����I �i2006.5.21 �F�쌫���Y�X�[�p�[�f�̗��K�n�߂�E�E�E�B�j |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.25 �ۂ���]�ʂ̖S��i�H�j �u��ւ��ɓ�A���v�ɂ��ĐF�X�v���`���Ă��܂����B��ւ����Ɋp�t�������܂��͂����Ȃ��̂ł��B���̂����A��̂͐�ւ��̐����ŒJ�ֈړ����܂�����A�G�߂ɑ������S�������邱�ƂɂȂ�܂��B�x�т�f��Ȃǂ̃P�K�������Ă��邱�Ƃ͊m���ł��B�i���̒m���Ă���l�ł��������邱�Ǝ��̂��ُ�ł��E�E�E�B�j ���āA�^�[���̌㔼�����ʼn����l���Ă��邩�H�Ƃ������Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł����A�v���Ԃ��ƁA�R���̕����i���ԁj�����\�������ƂɋC�t���܂��B���X�Ɖ�葱����悤�ȁi����Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ��̂ł���)�A����ȍ��o������܂��B�����ēr���ʼn�ɋA���āu��ւ��Ȃ�����I�v���Ă��Ƃœ��삷��̂ł��傤�ˁE�E�E�B �́X�A�u�ۂ���]�ʂ�`���v�Ȃ�Ă��Ƃ����o��������܂��B�Y��Ă��܂������A����̎v�l�Ŏv���o���܂����B�܂�A��̂͒J�i�ߑO���j�֒����I�Ɉړ�����̂ɑ��A�X�L�[�������̖@���ʼn�]�𑱂���̂ł��ˁB�����čŌ�̕����ł���]�𑱂���̂ŁA�u�ۂ���]�ʁv�Ɏd�オ���Ă��܂��悤�ł��B���ꂪ�p�t�����͂���Ȃ������ł��傤���H ���Ă��Ƃ́A�����ɂ܂����āi�t���[�Y���āj�����l���Ă��Ȃ��I���Ă��Ƃ��ؖ�����Ă��܂��܂����B�i������I����ȁI�j �u�ǎ��i�^�[���j�|�W�V�����ɒ��ӂ��邱�Ɓv�Ɏ���u�������Ă����悤�ł��ˁB�u�ꏊ�����ɂ�肷����Ƒ�ςȂ��ƂɂȂ�܂���I�v�i���������Ȍ������Łj�B ��̂̈ړ������ƃX�L�[�̌��������킹�����������ł��ˁB���߂��Ȃ��悤�ɕ����������킷���Ƃ������C���[�W���Ă݂܂��B����ƁA�O��̎ʐ^���Q�l�Ɍ��Ă��������B�E�X�g�b�N�̃����O��O�ɏo���āA�^�C�~���O�����v�炤�悤�ɑ҂��Ă��܂��Ă��܂��B�܂�A�t���[�Y���Ă���̂ł��B�X�g�b�N�̃����O��̂��O�ɏo��������̂��֕��̂悤�ł��ˁi�n�C�X�s�[�h�ł́j�B�p�t������������A�p�t�����͂������Ƃ����Ă���͂��Ȃ̂ɁE�E�E�B�p�t��������K���邭���ɁA�͂������K���Ȃ��̂͂Ȃ�ł��낤�E�E�E�B ����͊����X�s�[�h��}���āA�u��]�i�^�[���|�W�V�����j�v���u���i�i��ւ��j�v�E�E�E�B���ɐ�ւ����n�߂�^�C�~���O�𑁂߂Ɏ�邱�Ƃɒ��ӂ��Ă݂����Ǝv���܂��B��]�����i����]�����i�E�E�E���J��Ԃ��ƁA�n�[�g�^�̉�]�ʂɂȂ肻���ł��ˁA��������I |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.26 �����}�I�肯�������͗l�ł��i�S�z�E�E�E�j ���W�r��̃X�L�[���[���������Ă��鐯���}�I��A�X�[�p�[G�̃g���[�j���O���ɉ��䂵���݂����ł��B�S�z�ł��E�E�E�B�����ƌ��ꕜ�A�܂ʼn������Ă��܂��E�E�E�B �����}�t�@�� |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.27 �������X�L�[���
�O��܂ł̓f�W�J���iCASIO EX-Z600�j�̓���ŎB�e���Ă����̂ł����A�{���̓f�W�^�����[�r�[�J�����iSANYO DMX-HD1�j�ɂĎB�e�B���w�P�O�{�A�f�W�^���P�O�O�{�̃Y�[���͊����܂œ���ł��E�E�E�B�f�W�^���r�f�I�{�p�\�R���ɂẲf�����͂͗������P�O�O�{�ł��ˁB����ɁA���悩��A���Î~��������쐬����ASICS�̃f�W�^�����[�V�������g�������Ȃ̂Ō��ݖ₢���킹�Ă��܂��B�i�ǂȂ��������p���̕���������Ⴂ�܂�����A���슴�ȂNj����Ă��������E�E�E�B�j ��͂�A�n�[�g�^�̉�]�ʂ��C���[�W����Ɠ����₷���Ȃ�܂��E�E�E�B ���������P�̒���������܂����E�E�E�B ����ɂĐV�����ł̊���[�߂ƂȂ�܂����B����͌��R�ɂĎB�e�g���[�j���O�ł��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.5.30 �A�X���[�g�̒�� ��N�n���̎w���҉��Â����ƂĂ����ɂȂ����u�K��ɎQ�������܁A���Z�ŋ��Z�X�L�[���̖ʓ|�����Ă���搶������I��̊��������Ƃ��āu�J���p�v�����Ă���p�Ɋ������A�����Ȋz�ł͂���܂������A�J���p�Ƃ����s�ׂ������Ă��������܂����B ���̑I�肩��A�u�J���p���肪�Ƃ��������܂����v�̓��e�̂������ȑO���������Ă͂���܂������A����A�u���x�����肪�Ƃ��������܂����v�̂���V�[�Y���I���ƂƂ��ɓ͂��Ă���܂����B���������e�Ɂu�o���Ȃ����v�ƌ����ĂƂ͎v���܂����A��������Ǝ����̎��ŏ����ꂽ���t�ƁA�傫�ȑ��ŗD���������̎ʐ^�ƁE�E�E�A���ӂ���S�̕\���̎d���Ɋ�����������ł��B �g���m�I�����s�b�N���e���r�Ŋϐ킵�āA�e�I��̎����O�̃C���^�r���[�₻�̐��тȂǁA�O�X���犴���Ă����̂ł����A�r��Í��I��̋����_���ɔ[�����Ă��܂����B ���Z�Z�p�̋Z�ʂ��ύt�����I��̏W�c�ł����Ă��A�D���܂��B���̍��͉��ł��傤���H ���W�r��̃X�L�[���[�͍l���܂��B���̕���_���Ă��̐l�������Ă���u�l�ԗ́v���ƁB����̓I�����s�b�N�Ȃǂ̍��ۑ��ؖ����Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��B �q�ǂ��B�Ɋw��ł��炤�̂́A���Z�Z�p�����ł͂Ȃ��A�A�X���[�g�Ƃ��āi�l�ԂƂ��āj�����Ă������߂ɐ��������Ƃ͉����Ƃ����悤�ȁA�S�̔��B�ɂ��w���҂͖ڂ������Ȃ�������Ȃ��A�Ǝv���̂ł��B�������͍D���ł͂���܂���B�����ƌ����������Ƃ����H�ł��邩��u�X�L�[�v���D���Ȃ�ł��ˁA���B ���W�r��̃X�L�[���[���������Ă��鐯���}�I�肪�A�����܂����B��������ƃ��n�r�����Ă��������A���܂ňȏ�̊�����F�O���Ă���܂��B�����̌����Y����ɑ����`���I �����}�t�@�� |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
���y�[�W�̐擪�� ���ŐV�̋L���� |
2006.6.2 �\��i�H�j �t�X�L�[�͎B�e�g���[�j���O�ɖ�����ꂽ��ł����A�B�e�����摜���p�\�R���ŃR�}����ɂ��A���Ȃ��Ȃ��猩�Ă��鎟��ł��B�����ŋC���t���̂ł����A�g�b�v�I��Ɩ��炩�ɈႤ�Ƃ��낪����܂����B ����́A��̕\��ł��B �g�b�v�I��͏�ɂ��̏�̎���ǂ݂Ȃ���i���p��Ńt�B�[�h�t�H���[�h�j�A�ڐ������̃t�B�[���h�ɒ�����Ă��܂��B����ɑ��A���W�r��̃X�L�[���[�́A�u������I���܂����I�v�Ƃ��u����I�ǂ����悤�I�v�Ƃ��̈ӎ��i���p��Ńt�B�[�h�o�b�N�j����̕\��ɂ�����Ă��āE�E�E�A�����A�c�\������Ă��܂��Ă���̂ł��i���`���I�͂��������E�E�E�j�B �u������I���܂����I�v�Ǝv�����o���������Ƃ��Ă��A���̓���𑱂��āA���s���ŏ����ɐH���~�߂�ɂ́A�u��̕\��A�d�v�����I�v�A�u�Ƃ��Ă��d�v�����I�v�B�������Ȃ��������̂悤�ȁA�j�̃_���f�B�Y���E�E�E�B ����ȏ����w�E���ł���f�W�^���ȉ摜�ł��B����́u���v�̋��n�ɓ���Ȃ���A�j�R���J�ɂł���Ί���̖{�����ς���Ă��邱�Ƃł��傤�E�E�E�B����ς�A���R�Ńg���[�j���O�ł��傤���E�E�E�H �i����ĂˁE�E�E�j |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.4 ���R�X�L�[���
��D���ȑ�R�[�X�ɂ��Ⴊ��R����A�I������̃g���[�j���O�ł����B��ւ������P�̒������E�E�E�B �i�����̓j�R���J�ȕ\��ŎB�ꂽ�݂����ł��E�E�E�B�j ���t�g�~���e�Ŏʐ^���B���Ă݂܂����B���R�̏����ȏ����ȉԂ����ɍ炢�Ă��܂����̂ŁA�����E�E�E�B �ł��A�ʐ^���B�邩��ƂP���Q�����݂��߂�ƁA�����ɂ������ȉԂ������E�E�E�B ���R�X�L�[��͍����������ɂ���܂��B���R�݂͂�Ȃ̂��̂ł��B��ɂ������ł��ˁB
�R�`�������R�������i�u�Â��猎�R�֏オ�铹�ɓ����Ă��獶���ɂ���܂��B�j �@�Z���@��990-0734�@�R�`�������R�S���쒬�厚�u�Î��W���x�P�T�X �@�d�b�@�O�Q�R�V�|�V�T�|�Q�O�P�O�@�X�F�R�O�W���Ŗ�Q���ԁA�����Ő����Ȃǂ����邻���ł��B �Q���Ԏ��R�ώ@���Ă���A�ߌ㌔�Ŋ���Ɩ{������t���ꂻ���ł��ˁA���ɓ��j���́E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.7 ���ȊO�݂͂�Ȏw���� �������NALPINE SKI �̗p��̕ω��ƁA����������Z�p�E���@�_���傫���ς���Ă��Ă���Ɗ����Ă��܂��B���̓��e�́A����Ȃ��l�����������͂���ł͂Ȃ��A���̗p����g���āi�g�����Ȃ��āj����Ă����Ⴂ�l�X�̊��肻�̂��̂����邱�Ƃɐs����Ǝv���̂ł��B�ł�����A���{��\�ƂȂ�I��̊����������A���[���h�J�b�v�Œ��_�𑈂��Ă���I��̊����������B���̊�����������̂ł����A�������������ATV�ϐ��DVD�ӏ܂ƂȂ鎟��ł��B ���遁������A�u�l�ԗ́v�����߂邽�߂ɁA�����g�̂���S�����Ă��邱�Ƃ̈�ł��B���̏�ɋ��āA���������邩�A�����邱�Ƃ��ł��邩�B�����āA���������������A���̏�ɍs���Ƃ������ƁB�p�\�R��������Ή��ł����ɓ���킯�ł����A����ȏ�ɁA���̏�ɋ��邱�ƂŁA��C���甧���犴���邱�Ƃ����X����܂��B�����Ă��̎��̕]�_�͌ォ��K���������Ă�����̂ł��B �ŋ߂̂��C�ɓ���f���́A���鍑�̃W���j�A�`�[���̃g���[�j���O�B�t���[�g���[�j���O��������A�Q�[�g�g���[�j���O��������B���Ă��ĂƂĂ��C�����������v���ł��B �䂪���̃`�[�������E�̏�ʂ𑈂��悤�ɂȂ�܂����B�e�l���v���Y�݁A�����Ď������Ă��邱�Ƃ��ƂĂ��M�d�Ȃ��Ƃ��Ǝv���̂ł��B���������`�[���̃g���[�j���O�f���W������Ĕ̔����Ă���Ȃ�������H�����Ƃ����Ƒf���炵���I�肪�e�n����o�Ă��邱�Ƃ����҂ł��邵�A����グ�͑I�芈���̎����ɂ��Ȃ�͂��B�f�����J���Ă��A�����l����������ɂ͖{�l�̓w�͎���Ȃ̂ŁA�閧�ɂ��Ă������R���Ȃ��Ǝv���̂ł����E�E�E�B�o���甃���܂��E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.8 �ς��Ȃ����� �����D���ȊG�B���̐́A���R�ŏ��F�b��f���ɋ���������ƁB�X�g�b�N���X�L�[���[�Ɍ����Ăē������āE�E�E�B 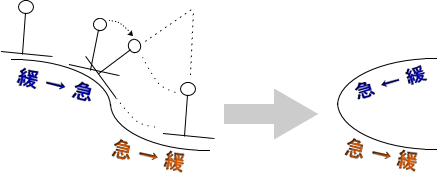 ���̐}�́A�ɎΖʁ`�}�Ζʁ`�ɎΖʂ��~���鎞�A�X���[�X�Ɋ��邽�߂ɃX�L�[���[�������Ή����@��\���Ă��܂��B �i�P�j�ɎΖʂ���}�Ζʂɕω����鎞�́A�������x�_�ɓ���J�ցB �i�Q�j�}�Ζʂ���ɎΖʂɕω����鎞�́A���̉�������̎x�_���C���[�W���U��q�̂悤�ɓ����B ����ŁA�o�����X�悭�X���[�X�Ɋ��邱�Ƃ��ł���Ǝv���܂��B �E�̐}�́A�^�[���������Ă��܂��B���̎Γx���~�^�����鎞�A�X�L�[���[��������Γx���������Ă��܂��B �͓̂����ɌX���x���������Ȃ������̂ŁA�����~�ł̑O��̑Ή����A�^�[���ł��߂����o���������̂��Ǝv���܂��B ���͓����ɌX���x�����������̂ŁA�O��̑Ή������ł͂Ȃ��A�RD�i���́E��ԁj���C���[�W�����ł����A ���̐}�������ɂ͂����Ȃ��͂��ł��B�Ζʂ��~�^�����Ȃ��痎�����Ă����̂ł�����E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.10 ���� �挎����n�߂����앪�͂����Ƃ����̂ɂ��ė��V�[�Y���̃��b�X�������ɐ������Ȃ����ƍl���Ă��܂����B ���A���J����̃u���O�������؋�����̃u���O�֍s������A���앪�͂Ɏg�p���Ă���\�t�g���Љ�ꂽ�����̂ŁA���̃��[�J�[�̃y�[�W�ցB�Ȃ�ƃr�b�N�X���������V�����X�|�[�c��Ȋw�Z���^�[�̕��̃R�����g���f�ڂ���Ă��܂����B  �Ƃ����Ȃ���Ŕ��������u�X�|�[�c�S���w���C��i��匤�C�j�v��������U��R�[�X�ɎQ���̋����������������̂ŁA�����Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.13 ���C��i��P���ځj ���j���̌��C��͂ƂĂ����ɂȂ�܂����B �Q���҂̎�ڂ��l�X�ŁA���ꂼ��̒c�̂�A���Ɏ����A����ʂ��o�������A�Ɛ^���ł��B ����̖ړI�́A�P)�X�|�[�c�S���w���w�т����B�Q�j�Q�O���N�X�L�[�w�Z�Ȃǂŏ����Ȏq�ǂ��������炨�N���܂ŐE�ƂȂǂ��l�X�ȕ��X�Ɛڂ��Ȃ�����H���Ă������e���A�ŐV���_�Ɖ��������ʼn����Ⴄ�̂���m�肽���B�R�j���ꂩ��̊����ɖ𗧂��Ƃ������邼�I�ƌl�I�ɂ͎v���Ă��܂��B ����̌��C�͘b�������łȂ��A���Z�������܂��B���C�J�n���̌��͂��猤�C�I�����ł̌��ʂ̕��͂܂ŁA������Z���s���A���̌��ʂ���������Č��C����̂ł��B�N��̃X�L�[���ԂŒ��w�Z�̐搶�Ƒ��k�̌��ʁA���̐搶���ē����Ă���V���s���̒��w���q�o�X�P�b�g�{�[�����̕��X�ɂ����͂����������邱�ƂɂȂ�܂����B�ł��A�������̃`�[���͑��ɕ����Ă��܂����Ƃ̂��ƁE�E�E�B������ƐS�z�ł��E�E�E�B�������ɗ��������ȁE�E�E�B�n���̃X�L�[���̐搶�ɂ����k���悤�Ǝv���Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.15 �w���@ �l�����I��w���������s���Ă��邱�ƂɂȂ�̂ł����A���̎w���@�̎�舵���̗ǂ������ɂ��ẮA������u���̕��ɋ�����Ă��܂��B�܂��A�e�B�[�`���O�ƃR�[�`���O���Ă���ς�Ⴄ���̂��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �P�O�N�قǑO�A�u���b�N�Z�p���̗F�l���b�M�z�n��̌��C��ɎQ���������̘b���Ă���A���������S�|���Ă��邱�Ƃ�����܂��B ���̎��̒S���u�t�͐X�M�V����B ����O�ɐ������āA�u�t����Ɋ���A�Q���҂��S������I���ꌾ�A �u���肪�Ƃ��������܂����B�v�i����I�A���ꂩ�玟�̐����ցE�E�E�j �����Ȃ̂ł��B���߂ĕ��������e���A�܂��͂���Ă݂悤�Ǝv���āA�����Ă���Ă݂�B�u����͂��₾�I�v�Ƃ����I���������钆�ŁE�E�E�B �P�O�^�[�����Ă݂ĂP�O�^�[���Ƃ����܂��o���Ȃ��Ă��A�u���肪�Ƃ��������܂����B�v�ƌ�����w���҂ł��肽���Ǝv���Ă��܂��B�Ώێ҂��q�ǂ��ł��A��l�ł��E�E�E�B�{�l����낤�Ǝv���A�g���C���Ă��邱�Ƃ������̂ł�����B �����āA�P��ł����܂��o�������Ƃ��u�J�߂āv���������B�o�����Ƃ�����т������������B������Q��ɁA�R��ɂ������A�Ƃ����{�l�̗v�]�ɉ����Ă��������B �w���@�̗ǂ������̐R�����́A��u�����Ǝv���̂ł��B �����āA���Ƃ����A��u���̕��ɍ��ł���ĂĂ��������Ă��܂��E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.18 ���R�X�L�[��� ICI�W����V�����ւ͂P�U���̋��j�ɖK��A���������ɍĉ�B�p�������܂��A���R�֍s���Ă��܂����B �O��ɋA�肪���Ɋ�����R�`�������R�������i�l�C�`���[�����h�j�ցB�H������̃K�C�h�Ńu�i�т��U��ł��B ���͋C�����ʐ^�Ŗ�����Ă��������B
�ߌ㌔�ŃX�L�[��ցB�ߌ�̓��t�g�҂��Ȃ��ŁA��R�[�X���g���[�j���O�B ���t�H�[�����C�����������ȍ~�́A�p�t�����ɂ߂邱�ƂɏW���B�̂̈ӎ��Ƃ��Ă͏�ɏ�̂�J�ɗ��Ƃ��Ă����C���[�W�Ńg���[�j���O�B�c��̉ۑ�́A���G���v�������������������ƁB�̌`�̉e���ł����A�Q�O�O�V�N�̓}�e���A���̒������K�{�ł��B
���������� �R�`�����͍]�s���L�Q�U�S�|�Q�@TEL 0237-87-1600 ���H�������̕��c�_������Łu�����сv���w������Ԃł��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.21 ���_���}����l���� ���E����Ɋ��邱�ƁA���{�̑�\�ɂȂ邱�ƁA�n��̑�\�ɂȂ邱�ƁE�E�E�B �w���҂����k�ɋ��߂���́E�E�E�B ���ʂ��S�ĂȂ̂ł��傤���H �w���҂ɂȂ肽���Ƃ����l�Ɗ���@������̂ł����A���t�g�Ɉꏏ�ɏ�������u���i������A�ǂ������w�����������悤�Ǝv���Ă���̂ł����H�v�Ƃ���������悭���Ă��܂��B ��̓I�Ɂu�q�ǂ������̃X�L�[�����̖ʓ|���݂����I�v�Ƃ��A�u�N���u�̌�y�����Ɏ����̌o����`�������I�v�Ƃ��A���i���������̓I�ɃC���[�W���Ď��g��ł���l�̕����A���i���������悤�Ɋ����Ă��܂��B ���͍��Z���̎��Ƀu���X�o���h�̉��t�œ��{��ɂȂ������Ƃ�����܂��B�Q��B���̎��A�N���Ƌ����Ƃ��A�������̊w�Z�ɂ͕����Ȃ����A�Ƃ��A����Șb�͈�x������܂���ł����B�i�����j�܂����{�̍����Ńu���X�o���h�łR�x�������t����Ă��Ȃ��Ȃ����ǁA������ǂ���Ă݂�H�E�E�E�w���҂����k�ŁA�w���҂ƂȂ�搶�����Ȃ������̂ɁA�F�Ŏ��g���Ƃ́u�������t�����悤�v�Ƃ����C���[�W��ǂ����߂�Ƃ������Ƃł����B �u���{�̑�\�ɂȂ邱�Ɓv���u����ō��i�_�̂V�T�_���߂������Ɓv�A���Ă��܂��B �Ƃ��ɂ��̃��C�����߂����Ă���Ƃ���E�E�E�B���̌�́H�E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.22 �C���[�W �A���y���X�L�[�̃C���[�W�g���[�j���O�́A�ǂ̃X�|�[�c��ڂƔ�ׂĂ��A���̏d�v���͍������̂��Ɗ����Ă��܂��B ���V�[�Y�������ɂƂ��ĉ����e�[�}�����߂Ď��g��ł���̂ł����A���Ȃ�ȑO�Ɂu�C���[�W�g���[���O�̎��ɏo�Ă���f�����Ăǂ�Ȃ́H�v�Ƃ������Ƃ����������ɐF�X�q�˂��V�[�Y��������܂����B �i�V���i���f����������A�X�L�[�w�Z�̐搶��������A��ʂ̎w�����̕���������A�e�N�j�J���v���C�Y��ڎw���Ă������������E�E�E�B �S�[���]�[�����猩�グ�Ă��āA�����Ɋ����Ă���f���E�E�E�B �X�^�[�g�ʒu�ɂ��āA�������猩����p�̉f���E�E�E�B �������������Ă����Ζʂ̉f���E�E�E�i�H�j�B �l�Ԃ̓��̒��ō�肠����RD�f�������̃X�y�b�N�́A�X�[�p�[�R���s���[�^�̔�ł͂���܂���B �S�[���]�[�����猩���������A�Ζʂ̉�����B�e�������̉f���ɕϊ�������A���t�g�ɏ�Ԃ��Č����낷�悤�Ȋp�x����̉f���ɕϊ�������E�E�E�B�����āA���̊����i���l�j�̒��ɓ��荞��ŁA���̐l�������Ă���ł��낤�u���o�v�������Ƃ��Ă݂���E�E�E�B�i�ł��A�Ζʂ̉f���͏o�Ă��Ȃ���Ȃ��H�j �����ŏ��Ɍ���̂́u�X�L�[�̓����v�ł��B �X�L�[���ǂ̂悤�ɐ�ʂɐڂ��Ă��邩�A�����͂ǂ����A��ʂ���̗͂̂������͂ǂ����E�E�E�B �ł�����A�C���[�W�g���[�j���O�̎��A�ŏ��ɏo������f���́A�u�X�L�[�P�̂������Ă���l�q�v�Ȃ̂ł��B �X�L�[���[�͏o�Ă��܂���A�X�L�[�������o�ꂷ��̂ł��B �X�L�[�Ƃ����X�|�[�c�́u�X�L�[������v�X�|�[�c���Ǝv���Ă��܂��B �����Ċ����͂��̓������ז����Ȃ��悤�ɉ�Y�����Ă����B �X�L�[���[������̂͂�����ł���ˁE�E�E�B ���̎��ɓo�ꂷ��̂́A�X�L�[�ɃX�L�[�C���t������Ԃ̕��̂������Ă��܂��E�E�E�B  �������肵�܂����B �i�w���}���E�}�C���[��������芊���Ă��܂����ˁE�E�E�B�j |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.24 �{���E���� �����̒m��Ȃ����Ƃɖڂ������A�����̕����L���邽�߂ɁA�N�ɐ�����p�قɏo�����܂��B�u���炵���v�ƌ����Ă���{�������āA���Ŋ����邽�߂ł��B �����͗[���u�V���������㓇���p���v�ɍs���Ă��܂����B ����̊��W�́u�x�I�O���[�h�������p�ُ����t�����X�ߑ�G��W�@��۔h�ƂQ�O���I�̋��������v�B ���l�A���m�A�[���A�S�b�z�A�S�[�M�����A�}�e�B�X�A�s�J�\�E�E�E�B �P�O�O�N�O�̍�i�A�������{���B�i�V���P�U���܂ŊJ�Âł��B�j �����̔��p�ق͍L���A�W�����������̂ŁA�P�_�ÂW�����Č��Ă���ƁA�Q���Ԃ͂�����܂��B �o�Ă���ƃt���t���ɂȂ��Ă����肵�܂��B �u���遁������v�A�u�����̒m��Ȃ����Ƃ�m��A�F�߂�v�A ������X�L�[�̏�B�ɂȂ��邱�Ƃ̈�ƐM���Ă��܂��E�E�E�B 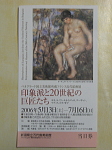 �V���������㓇���p�� �V���������㓇���p���V�����V���s���㓇�T�[�P ���łɁA���C�ɓ���̃A�[�e�B�X�g�����Љ�B�u�`���b�p�`���v�X�v�̕�ݎ����f�U�C�������u�T���o�h�[���E�_���v�B�ނ̍�i�͂�����ő�R���邱�Ƃ��ł��܂��B �����ߑ���p�� �������떃�S�k�������厚�O����������1093��23 �O�����f�R��L���X�L�[��̂��ł����A�~�G�͕ق��Ă��܂��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.27 ���Y���� �X�L�[�̏ꍇ�A�E�^�[���̎��ɍ��^�[�������āA��~����܂ł�����J��Ԃ��܂��B �����Ƀ��Y�������܂�܂��B ���Ԃ̊T�O�Ƃ����̂��A�l���ꂼ��Ɋ��������Ⴄ�����ł��ˁB ���̐́A�u���X�o���h�Ńp�[�J�b�V�����i�Ŋy��)��S�����Ă��܂����B���g���m�[�����g���A���Y�����̗��K�����܂��B �o�`��ł��ĉ����ł�u�ԂƁA���g���m�[����������^�C�~���O���������H�Ƃ������K���R���Ă��܂����B �����f�W�^���\���̘r���v���o�n�߂̍��ŁA�P�O�O���̂P�b���v���ł�����̂�����܂����B ������g���āu�P�O�D�O�O�b�v��\���ł��邩�A�ڂ��Ԃ��āA�Ƃ����V�т����Ă��܂����B ���̒��ɂm�g�j�e���r�̎���e���b�v���v���`���܂��B�����Ă��̔��M�����P�O��J��Ԃ����u�Ԃƃ{�^�����������^�C�~���O�����킹�܂��B �u�P�O�D�O�O�b�v���\�ł��܂����B �b����ł�����̂ł��B  �i���͎G�O���炯�łł��܂���E�E�E�j |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.28 ���Y�����@���̂Q ���Ԃ̊T�O�Ƃ����̂��A�l���ꂼ��Ɋ��������Ⴄ�����ł��B �v���싅�̃s�b�`���[���������{�[���̖D���ڂ��������Ƃ����b���悭�����܂��B ���̐́A���a�S�O�N��̉䂪�Ƃɂ͂r�n�m�x���̃I�[�v�����[���̃e�[�v���R�[�_�[������܂����B �e�[�v�͓��������i�ł����̂ŁA�u�W���̑��x�v�Ɓu�W���̂P�^�Q�̑��x�v�̐�ւ��X�C�b�`������܂����B �u�W���̑��x�v�Ř^�������������u�W���̂P�^�Q�̑��x�v�ōĐ�����ƁA���̃e���|�͔{�ɂȂ�܂��B ���a�T�O�N��ɍ��Z�����������̓v���̃h���}�[�̉��������̃e�[�v���R�[�_�[�ɘ^��A�{�̃e���|�ōĐ����Ă͕��ʂɏ����A���t���̂��̂��R�s�[���Ă��܂����B ��l�ɂȂ��Ă���A�g�����y�b�^�[�̓���ᩐ��������v���ɂȂ�܂łɎ��Ɠ������Ƃ����ėL���ȉ��t�Ƃ̃R�s�[�����Ă����A�ƃ��W�I�ŕ��������̓r�b�N�����܂����B �ǂꂾ���X���[���[�V�����̒��ŕ`���邩�E�E�E�B�P�^�P�O�b��������A�P�^�P�O�O�b��������E�E�E�B ���́A�T�����[���̃|�P�b�g�ɓ���n�C�r�W�������[�r�[�J�����ŎB�e�����l�o�S�t�@�C�����A�p���������s�������ł̃R�}����Ŋy����ł��܂��B�i�悢����ł��B�j�{���ɃN�b�L���͂�����X���[�œ����܂��B �i�䓌��̋斯��ق̂����痎�Ƃ��ŁA���̃X�e�[�W�ɗ����Ă������Ƃ́A���܂�m���Ă��Ȃ��E�E�E�B�j |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.6.29 �|�p �u�F�쌫���Y�̂͂Ȃ��v�ł́A���[���h�J�b�v�T�b�J�[�ɂ��ẴR�����g������f�ڂ���Ă��܂����B �����𐬂������鎖�̑O�ɂ͊撣�肪�����Ă����̂ł͑ʖڂ��Ǝv���B �i�����j�܂茻�����n�܂鎞�ɂ͓w�͂��܂߂Ċ撣��ƌ������m���|�p�ɕς���Ă����͂����Ɖ��͎v���B ���������A�������p�≹�y�ɂ��ďq�ׂĂ�����ł����A�Y�o������Ȃ̂ł��B ���鑤���u���炵���v�Ɗ�����Ƃ�����A����肪�v���`�����Ƃ������Ƃ��Ăł��������u�|�p�v�ƌ��������邱�Ƃ��ł��邩�炱���A�u���炵���v�Ƃ������z�����܂��̂��Ǝv���B ���y�ł���A �����o�����K�E�E�E�A ���̋���̗��K�E�E�E�A ���ʂǂ���Ƀ��Y���ǂ���ɉ��t������K�E�E�E�A ���ꂾ���ł͊ϏO�Ɋ����Ȃǐ��܂�Ȃ��B ���t�Ƃ́u���őt�ł邻�̑z���v���A�u�\���v�����邩��A������́u�����U�邦��i������j�v�̂��Ǝv���̂ł��B  �{���A�����s�X�L�[�A�����A����{�����ψ��̈Ϗ��͂��Ă���܂����B ���͂Ȃ�������P���A�X�L�[�E�̔��W�̂��߂ɁA����`�������Ă������������Ǝv���܂��B ���̃z�[���y�[�W�������ɗ����Ƃ��ł���E�E�E�ƁA����Ă���܂��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
���y�[�W�̐擪�� ���ŐV�̋L���� |
2006.7.2 �v���W�F�N�g�c �X�L�[���Ċy�����I ���łP�ԂɂȂ�����A�v���ǂ���ɂ��܂���������A������̕����y�������ǁA �r���ɂȂ��Ă��A���܂������Ȃ��Ă��A�y�����Ǝ��͊����܂��B ���낢��Ȑl�̃u���O���炽�ǂ蒅���������́u�p���_�C�X�v�I �R���������܂����X�L�[�N���u����̃T�C�g�B �v���W�F�N�g�c�A�X�L�[�i�E�f�O�V�A�ǂ̉f�����A�y�������Ɋ���f���ҏW�͈����I �͂܂�܂����E�E�E�B �u�f���p���v�Ƃ����ƁA�V�O�N����f�T���g�����甭�����ꂽ�u�f���p�� ���[�T�[�v�Ƃ������i�̃e���r�b�l���v���o���܂��B ����܂ł̃X�L�[�p���c�́A�u�X�p�b�c�^�v�B �^�C�c�Ɠ����ł�����X�L�[�C�̒��ɓ���܂��B���R�Ⴊ�C�̒��ɓ���܂��B �����A�̎u���̎q�ǂ������́u�r���i����͂�j�v�i�F�r�����̑��Łj��t���Ă��܂����B �H�Ɛ��i�̖�������ł��B�ꂪ�ю��ŕ҂�ł��ꂽ�����A�݂�Ȃ��t���Ă��܂����B ���ꂪ�A�X�L�[�C���ォ���݃J�o�[����X�L�[�p���c�̓o��ł��B ���̉Ƃɂ��܂��u�f���p���v����܂����B�i�̂Ă�ꂸ�ɁE�E�E�j �s�u�����ŕ��f���ꂽ�X�L�[�i�E�Ŏg�p���ꂽ�E�G�A���E�E�E�B |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.4 �w���@�@���̂Q �e�B�[�`���O�̋ɈӁB�Ƃ������A�S�����Ă��邱�ƁB����́A�@�u�Z���Z���e���X�v�@�Ő������邱�ƁB �ǂ̃N���X�̐l�ւ������B�������A��葤�������ł���\���ŁB ���������ȂǕs�v�ł��B���ꂩ�珉�߂Ă��鎖���A�Z�������ŁA�܂��́u����Ă݂悤�v�ł��B ����Ă݂āA���͂������悤�A�Ƒ̌����Ȃ���A�����āA�Ȍ��ɐ����ł��B �������鑤�ɂƂ��āA�u�Z���Z���e���X�v�͓����Ƃł��B �������A�K�v�Ȏ��͂���Ȃɑ����͂Ȃ��͂��ł��B �������鑤���A�������萮�����āA�������ɂ���u��Ȏ��v�ɋC�Â��A�u�Z���Z���e���X�v�͂ł��܂��B �ł����ł��B �ǂ����Ă������������K�v�Ȃ�A�Q�����f�ł͂͂��A�x�e���Ƃ�Ȃ��烌�X�g�n�E�X�ōs���܂��傤�E�E�E�B �w���҂̑��݉��l���āA����ȂƂ���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B  �����ɂ����܂����E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.7 ��̂̒Y�z�i��܁j�̎q �̎u���Ő��܂ꂽ�B��́i���݂����j�Ƃ����n��ŁA�������i���݂��傤�j�Ƃ�������B��������{���։���ƁA���i�V���i���`�[���̈ɓ����Ƃ���Z�킪�����̂����A�����͂܂��m��Ȃ��A�Ƃ������A�܂����܂�ĂȂ����������E�E�E�B ���w�Z�ɏオ��O�A�X�L�[���~�����āA�e�ɂ˂������B�܂��A�o�b�N���̕t�����C�͑��݂����A�Ђ��ŕ҂ݏグ��C�B��l�͔琻���������A�q�ǂ��̓S�����B�u�Ђ��ŕ҂ݏグ��ɂ͗͂������āA�܂��������v�ƕ��e�ɂ����Ȃ߂�ꂽ���A�u�����ł��邩��v�Ə��߂Ď��Ȏ咣�����A���ǔ����Ă�������B�A�W�A�X�L�[�̒P�̃X�L�[�������B �Y�z�X�̗l�q�͂P�X�V�V�N�ɏ�f���ꂽ�f��u�K���̉��F���n���J�`�v�i�B�e�F�[���s�j�̕��i�ɋ߂��B�܂��A�P�X�W�S�N�q�{���r�{�ɂ��s�u�h���}�u����A�ߕʂŁv�̕���ɂȂ����u�ߕʃ��}�����v�i�Q�l�F���� ������̃T�C�g�Ɏʐ^������܂����j�́A�K������S�W����喂�_��E�E�E���܂ɉf�悪��f������̂̉�ق������B �Y�z�̊e���ɂ͖����̑K�����������B�������ɂ��B�������͂r�`�i�̂Q���������Ă����B�����đ�l�����́A�K�����̎Ζʂ̖ɗ��d����A�˂āA�i�C�^�[�Q�����f������Ă��܂����B���w�Z�ɏオ��O�̎����A���ɘA����ėǂ����������Ƃ��o���Ă���B�i���Ƃ�����q�ǂ��̎��ɂ����Ŋ������A�ƌ����Ă܂����ˁB�j �V�Ⴊ�ς���ƁA�F�ʼn��ɂȂ�сA��݂��߂Ȃ���o���Ă����Əo���オ��u�s�X�e�o�[���v�B �X�L�[�ł̗V�т͒N���l�����̂��A�Ăі��͖Y�ꂽ���A�u�f�����X�g���[�V�����v�̃Q�[���������B�e�����߁A�e���������Ƃ���ɊF������Q�[���B�e�͊F���ł��Ȃ����낤�Ƃ������Y���i�V���v�[���j�Ŋ���B���̃V���v�[����ǂ��B�S���ł�����e�̕����A��̍Ō�ɕ��ԁB���̎��ォ��u�܂˂�v�Ƃ������Ƃ��n�܂����̂�������Ȃ��E�E�E�B �S�O�V�[�Y���ڂ̏I��荠�A�e���������Ă��܂����B ���~�ɂ͌̋��̋�C�ɐG�ꂽ���Ǝv���Ă���B �������̔����k���Ă���ƁA���L�̉����������������Ă������Ƃ��v���o���E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.8 ��̂̒Y�z�i��܁j�̎q�@���̂Q ����������V�h���i�������܂��j�Ɉڂ�Z�B����̘[���B���w���͎q�ǂ������A���w�N�̂��Z��������N���̖ʓ|���悭���Ă��ꂽ�B�Ă͖싅�A�~�̓X�L�[�̗V�т��������B ���w�Q�N���̎��A�X�L�[�c�A�[���v�悳�ꂽ�A�q�ǂ����������ŁB �V�h������R��o���ƁA�ԕ��R�̃X�L�[��ɏo��Ƃ̂��ƁB ���J�삳��A���c�����[�_�[�������ƋL�����Ă���B�Ⴊ�~�����璆�~�̖��������A�Q���̌����L�O�̓����������Ǝv���A�s�[�J���̐��ꂾ�����B �c�A�[���n�܂�ƃ��[�_�[�����͎���������������ƃT�|�[�g���Ă��ꂽ�B���X�ɁA�Ԃ��r�j�[���̕R���Ɋ����Ă��āA�ڈ�ɂȂ��Ă����B�����Ƒ�l�����ƃ��[�_�[���������A�������}�����̂��낤�B �r���A�ڂ̑O������u�G�]���X�v�B��������擱���Ă���u�������̑��Ձv�B�Ă͖�������A���邱�Ƃ̂ł��Ȃ��R�Ȃ̂����A�Ⴊ����������Ă����B����̋x�e���J��Ԃ��Ă͂������A��������Ɠo�肫��A�ԕ��R�̃X�L�[����ቺ�ɖ]�ނ��Ƃ��o�����B���̌��i�͍��ł��ڂɏĂ����Ă���B �����ăs�X�e�R�[�X�ɏo���B �����ԃX�L�[��Ŋ���A�A��͗����R�[�X���t�ɂ��ǂ����B �I�t�s�X�e�̃R�[�X�Ȃ̂����A�����͂����̊��ꂽ�V�`���G�[�V�����B�A��͍s���ƈႢ�A�����Ƃ����ԂɉƂɒ������ƋL�����Ă���B ���̌�͐ΒY�Y�Ƃ̒�����ɓ���A�F�B��������z���ŏ��Ȃ��Ȃ��Ă������E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.9 ���Ƃ̖� ���܂�ď��߂Ċ������X�L�[���́u�������x�v�B�u��́i���݂���)�v����H���o�X�ɏ��A�R�̘[�́u�̐_�i������j�v�ō~��A�R�܂ŃX�L�[��S���Łi������āj�����ēo�����B �����ɂ̓��t�g�Ƃ����֗��Ȉړ���i���������B�R�����グ�A�E���Ɂu�V�����b�v���t�g�v���P������B �i�����͊����グ���̃P�[�u���ł͂Ȃ��A�������[�v�̐�ɍ����~�Ղ��t���Ă��āA�����ځi���K�j�ɂ͂���œo�����̂ŁA���K�̕ӂ肪�G��ė₽���Ȃ�̂������E�E�E�B����Ă���ƁA���ɂ͂��ޑO�Ƀg���g���Ɛ���Ă����邱�Ƃ��o����B�j ���̂悤�ȃ��t�g�œo���Ă��鎞�Ԃ��D�����B �������x�ɂ̓��[���b�p���ɋ}�Ζʂ��オ���Ă����Q�l����T�o�[���t�g������B ���R��T�o�[�������B ����́A�X�L�[�̊����ʂ��t���b�g�ɂȂ��Ă��邩���`�F�b�N�ł��邩��B�����~�ł͕|���Ċ����Ă���q�}�͖������A�t���ł͐S�𗎂������đ������o���������܂����Ƃ��ł���B ��Ԓ��̃o�����X�����X�L�[�ɂ͗����B���̃��t�g������ƁA�x��ł���q�}���Ȃ��Ȃ邩������Ȃ��B ���̃^�C�v�̃��t�g��ݒu����A�u�X�L�[���[����Ă�X�L�[���v�������邱�Ƃ𖧂��Ɋ��҂��Ă���E�E�E�B �i�`�F�A���t�g�ɏ��߂ď�����̂́uFurano�F�����͖k�̕�X�L�[��v�ł����B�j ���w�Q�N���̎��A�������x�ōu�K�����J�Â���邱�Ƃ�m�����B������Q�������߂�ꂽ�B �d���̓s���ŕ��͍s���Ȃ��Ȃ����B����K�ꂽ�s������l�œo�邱�ƂɂȂ����B �m��Ȃ���l�̐搶�ɃX�L�[�������Ă����������B �u�v���[�N�{�[�Q���v�u�V���e���N���X�`���j�A�v�u�p�������N���X�`���j�A�v�B �����̎��͗F�B�Ƃ́u�f�����X�g���[�V�����Q�[���v�̂������ŁA�u�p�������N���X�`���j�A�v�Ŋ����悤�ɂȂ��������B �������A�䗬�B�u�p�������N���X�`���j�A�v�Ŋ��邱�Ƃ��ł���u�R���v�ɍ��i���邱�Ƃ�m�����B ��l��������́u�R���v�����߂�ꂽ���A�o���̎��A������u�S���v����Ă݂邩�A�ƌ����Ă����B �����ƁA�S���Ȃ獇�i���邾�낤�Ǝv���Ă������炾�Ǝv���B���i����A�F�߂����т������Ăق����Ǝv���Ă����̂��낤�B �u�S�����܂��B�v�ƌ����ėՂ݁A�ΐF�̘Z�p�`�́A��̌����̌`�������o�b�a�������������B �d������߂������Ƀo�b�a����������A�ƂĂ��J�߂Ă��ꂽ�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.11 �V�䃊�]�[�g�i�V�����j �V�䃊�]�[�g�^�c��Ђ����U�ƂȂ����|�V�����[�J���̃j���[�X�������Ɍ����B�i�V������̋L���͂������j ���ɗ����B�u���S�҂ւ̎w���@�Ǝ��_�v�i2006.7.1�j�ɂČ��O���Ă������Ƃ������ɂȂ��Ă����B �{���Ɂu�X�L�[�����邱�Ǝ����v�������̉��̈�l�ł������̐l�ɓ`�d���邱�Ƃ����Ȃ��ƁE�E�E�B �g�߂Ȑl����l�A��ăX�L�[�ɍs�����I �����āA�|���Ă����Z�p���A�����̂��߂Ɏ�������i���A�{���ɖ𗧂ĂȂ�������Ȃ��������Ă���̂��I ���łɊ����l�ɑ��āA�d���̋��₻�̊O����˂����悤�Ȋ��������A�u�^�ɃX�|�[�c�Ƃ��ẴX�L�[�v�u�ǂ�ȎΖʂł����邱�Ƃ��ł���X�L�[�v�u���R�i����X�L�[�v���y���ފ���������`�����Ȃ���E�E�E�B ���̂R�̃X�L�[�������T�|�[�g���邽�߂ɂ́A������������������āA�傫�Ȓc�̂̋^�킵���b���x����Ă͂����Ȃ��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.12 ���{�X�L�[�����ɖ]�ނ��� ���畔�w���������邽�߂ɓǂ܂Ȃ�������Ȃ��{�̈�ł��B ���̊�]�Ƃ��ẮA�ҏW�ψ��̒��Ɍ����i�V���i���f����A���Z���̃i�V���i���`�[���R�[�`�Ȃǂɂ��Q�����������A�w���E�ŏ����߂̊�b�x�荞��ł������������B�������ʎw�����̐搶���ɍs�����C��Ŏ��グ���y�������s�����ƂŁA���{��\�`�[���̐��삪�L����̂��Ǝv���B �A���y���X�L�[�Ɂw���畔�x�Ƃ��w���Z���x�Ƃ��̋敪�������Ă��ǂ����A�ǂ�ȕ������猩�Ă��w�A���y���X�L�[�x�ɕς��悤���Ȃ����̂ł���B �i�������A���܂ő����Ă���w���������o�b�a�e�X�g��ے肵�Ă����ł͂���܂���B����Ȃ镁�y��]��ł���̂ł��B�j �F�Ŋ�@���������Ȃ��ƁA�q�ǂ��̐l�������Ȃ����A�I�肪���Ȃ��Ȃ�܂���I ���W�r��̃X�L�[���[�͊C�O�̎���͒m��Ȃ��̂ŁA�e���̎��g�݂Ȃǒm���Ă��������������Ⴂ�܂�����A�����Ă��������B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.14 �v���y���^�[�� �q�ǂ��̍�����u�����^�[���v����肾�����B���w��������ł����̎�ڂ́u�V�O�D�O�v�ŃM���M�����i�������B �i�̂͂����炩�ŁA���i�E�s���i�Ƃ��N���u���Ăɓ_�������������Ă��Ă����B�j ���w��������ɍ��i�������ĂɌ��R�֍s�����B���F�b��f���ƈꏏ�Ɋ��������ɁA�W�����v�^�[���ɂ�鏬�����g���[�j���O�����B�u�X�L�[�S�̂��ʂ��痣���āv�u�g�b�v���グ�āv�u�e�[�����グ�āv�B �S�R�ł��Ȃ������B �R���~��Ă��Ă���A�u�Ȃ��ł��Ȃ��낤�v�u�ǂ��������ł���̂��낤�v�Ƃ����̂��l�����B �����̃X�L�[�����ɏ�����Ă����u�w���̌����v�Ƃ������ڂɁA�u�₳�������̂��������̂ցv�Ƃ����̂�����܂����B ���̎����ɂƂ��āA�u�ł��Ȃ����Ɓv���u������́v�B �ł́A�u�₳�������́v���Ă��̏ꍇ�ǂ��������̂��낤�E�E�E�B �P�j�Ζʂ͓���ȁ@���@���n�ł���Ă݂悤�B �Q�j������t���Ă͓���ȁ@���@���͂����Ă���Ă݂悤�B �R�j�X�L�[�C�͏d���̂œ������炢�������ȁ@���@�^���C�ŎŐ��̏�ł���Ă݂悤�B  �ܐ�̑O�ɉ������C���[�W���Ă݂܂��B  �W�����v���ċŌ�����ς��A���n���܂��B ���̌��������̂܂܂ɂ��āA�Ҋ߂��r��P�銴�o�ł��B ���n������A���̌������m�F���Ă݂܂��傤�B �^�[���̓����ƂȂ���̂ܐ悪�v�������P��ʂ�����Ȃ�������A�^�[���̊O���ƂȂ���̂ܐ悪�v���������P�肷���Ă�����E�E�E�B �����̎v���ƒ��n�̌��ʂ��Y���Ă���Ȃ�A��t���Ă�����A�g�b�v�����d�Ȃ�����A�e�[�������d�Ȃ����肵�Ă��܂��܂��B�u���E�̑��̌����������ɂ���v���Ƃ��ڕW�ł��B �ł炸�A��������Ɗώ@���Ă݂܂��傤�B  �܂��A�����͗ǂ��Ă��A�������������ŏ��ɐݒ肵�����ƃY���Ă��܂�����A ���̌������ꏏ�ɕς���Ă��܂��B�E�G�X�g��������P���Ă��銴�o�ł��B �����ǂ��Ƃ��邩�A�����Ƃ��邩�́A�F�X�ȍl��������Ǝv���܂����A �g���[�j���O�ő�Ȃ̂́A �����̎v���ʂ�Ɏ����̑̂������Ƃ��ł��邩�A ���̉^���ʂ��v���ʂ�ɒ����ł��Ă��邩�A �Ƃ������ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�ǂ�����v���ʂ�ɂł����猋�\�ł��B �g���[�j���O�̗l�q�𐳖ʂ���r�f�I�J�����ŎB�e���A������Đ��Ō��Ă݂܂��傤�B ���ɓ����Ă���l�́A������オ���肵�č��E�Ƀu���܂���B�f���̏�̂̃u����̓o�����X�̃u���ƍl���܂��傤�B �����|�C���g�ɂ��܂����n�ł���悤�ɂȂ�����A���n����ꏊ�������O���Ɏ��A�O�i���Ă݂܂��B �ǂ�ǂ�O�i���Ă����ƁA�Ζʂ����銴�o�ɋ߂��Ȃ�܂��B ���̎����Ɏ��Ԃ������āA�W�b�N���[������܂Ńg���[�j���O������A���ŗ��z�I�ȓ������R��ڂłł��Ă���͂��ł��E�E�E�B�i�C���X�g���u���Ă���̂͂��e�͊肢�܂��B���܂��ł���悤�ɂȂ�����A�����͂���ɃX�g�b�N���[�N�̃g���[�j���O�������Ă��܂����B�j �����グ��Ƃ�����Ƃ̏o���_�ɂ́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.17 ��̂̒Y�z�i��܁j�̎q�@���̂R �~�̗V�т̓X�L�[�B�����h�Z����u���Ƃ����ɒ��ւ��āA�����܂ł̒Z�����Ԃ��ő���y�������ƁA�����ǂ���яo���Ă����B�R�Ɉ͂܂ꂽ�X������A�����鏊�ɎΖʂ�����A������肾�B �u�f�����X�g���[�V�����Q�[���v�̑��ɂ悭����Ă����̂��u�W�����v�v�B ���������Ő���W�ߓ��ł߁u�W�����v��v�����B�������A�N�������ɔ�ׂ邩�A�������킯���B �i���ł��{�[�_�[�̕��X�͑�����y����ł���̂��������܂��B����ʂ�߂���Ƃ��A�u�����A����Ă����Ă�A�y������ˁA����I�v�ƐS�̒��łԂ₢�Ă����肷��B�j ��̉��ӂ�œ��ݐ������B���̏ꏊ�������Ă��x���Ă������ɂ͔�ׂȂ��B�ォ�犊���Ă��āA�^�C�~���O�����킷�̂��B�i���������A�X�g�b�v�E�H�b�`�Ń^�C�~���O�����̂Ɏ��Ă���E�E�E�j�����āA�R�`�T������Œ��n����B �V�т͐i�����Ă����B�R�`�T������ł�������A�撣��T�`�P�O���ʔ�ׂ�悤�ɂƁA���傫�����Ă����B �������̍���̘[�A�����ɂR�O�����̃W�����v�䂪�������B �V�����c�F�͖ؑ��B���ݐ�����f�B���O�o�[���͎Ζʂ̒n�`�����܂��g���Ă����B ����̃V�����c�F�́A������Ă��܂��̂ŁA���N��C������Ă����B �����������S�ւ̔z�����������Ǝv���A�u�q�ǂ����������ōs���Ă͂����Ȃ��v�A�����[�J�����[���������B �����������ƂŖ����g���Ă����ł͂Ȃ��̂ŁA�����ł��F�œ��ݏグ�Ȃ��烉���f�B���O�o�[����o���Đ��n���B ��̗ʂɂ���Ă͊���~��āA������x���ݏグ�邱�Ƃ��������B �V�����c�F�ɏオ��ƁA��������������Ă�����Ƃ͌i�F���Ⴄ�B��͂�r�r���Ă��܂��B �����T���߂ɏ������������A�����������A��Ԃ��ƂɊ���邱�Ƃ���n�߂�B �X�s�[�h������Ȃ��ƁA�����f�B���O�o�[���̓y�蕔���ɒ��n���A�Ȃ��Ȃ��Ζʂ̒��֗����Ă����Ȃ��B ����Ă���ƁA�V�����c�F�̈�ԏォ�犊��n�߂Ă����E�E�E�B �A�|���P�P�������ʂɒ�������O�̓~�̏o�����ł����B�����̃W�����v��͍��͂���܂���B ���̃W�����v���A�Q�����f�V���v�����O�i�ʏ̃Q���V���v�j�Ƃ��������ڂƂ��đ��݂��邱�Ƃ��A���N��ɒm�邱�ƂɂȂ�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.19 �v���[�N�{�[�Q�� �Ƃ����A�C�a�r�G������v���o���B �W�O�N��O���̃X�L�[�G���Ɍf�ڂ���Ă����L���B���[���h�J�b�v�ɏo�ꂵ�Ă������̊C�a���A�v���[�N�{�[�Q���̃|�W�V��������A��̂͂��̂܂܂ɕБ����āA�p�������|�W�V�����ɕω����邱�Ƃ��Q���̎ʐ^�ŕ\�����Ă��܂����B����Ȉ�ۂł����B 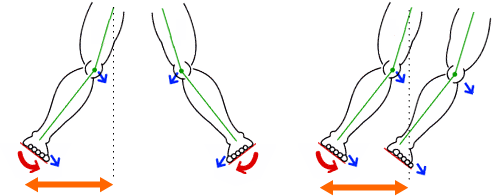 ���ł��A�v���[�N�{�[�Q���́A���S�҂����S�Ɋ���Z�p�ł���ƂƂ��ɁA�^�[���̌��^���Ǝv���̂ł��B ����́A����i�X�L�[�j�ƌҊ߁i���j������Ă��邱�ƁB�i�������`�����j �Б����邾���Ȃ̂ŁA���́u�������`�����v�͕ς��Ȃ��͂��B �͂����ăp�������^�[���Ŋ��鎞�ɁA���́u�������`�����v�������Ă��邾�낤���H �u�������`�����v���Z���Ȃ��Ă��Ȃ����낤���H �O���Ƃ������ƂŒ��ڂ���ƁA�܂�����Ȃ��^�[���|�W�V�����ł���B ���̃|�W�V�����ɔ@���Ɉړ����邩�A�Ƃ����̂��A�p�������^�[���̉ۑ�̈�ł͂Ȃ����낤���H ���̋������������邽�߂ɁA�����ƃv���[�N�{�[�Q���Ŋ����Ă݂悤�I �����Ƃ����ƁA���S�҂��w�����鎞�Ԃ��Ƃ�ƁA�p�������^�[���������Ƃ����Ə�B����̂��A�Ǝv���Ă���B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.20 �v���y���^�[���@���̂Q ���n�ł̃g���[�j���O�Ƃ��āA�W�����v���ċŌ�����ς��`���n����v�̂͑O��q�ׂ��Ƃ���ł��B �����ŕʂ̊ϓ_���璍�ӂ��������ƁB 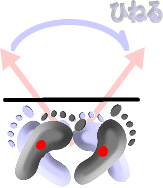 �i�P�j���n�`���n�܂ŁA�Ƃ����^�����C���[�W����ƁA �}�L�V�}���`�}�L�V�}���܂Łu�傫���Ђ˂�v�Ƃ������o�ɂȂ�܂��B ���̗v�̂ł͒��n�|�C���g���ʒu�ɒ������邱�Ƃ�����B ���̏ꍇ�A�Ђ˂鎞�Ԃ������̂ŁA�}�L�V�}���̏ꏊ�Łu�x�e�v���邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B�ł�����A���ۂ̊���ł́A�^�[���̌㔼�ɋx��ł��܂��A�Ȃ��Ȃ���ւ��ł��Ȃ��`�^�[���̑O�����̃��Y���������Ȃ�܂��ˁB �@�@�@������ƁA�ϓ_��ς��Ă݂܂��傤�B 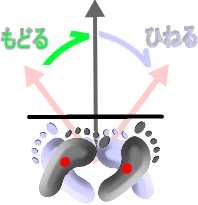 �i�Q�j�O���Ɍ����Ă��邱�Ƃ���ƍl���܂��B �i�Q�j�O���Ɍ����Ă��邱�Ƃ���ƍl���܂��B����ƁA �u�Ђ˂�v�Ƃ������o�A�ʂ��A��L�}�ɑ��Ĕ����ł悢���ƂɂȂ�܂��B �����āA�}�L�V�}���ł͋r���Ə�̂��Ђ˂��Ă����ł��B ���́u�Ђ˂��Ă���v��Ԃ���A�u���ɂ��ǂ��v�Ƃ������o���g���Đ��ʂ������܂��B ���̓�����A������ƁA�����̗͂��g���^�C�~���O�������ɂȂ�܂��̂ŁA�Ƃ��Ă��ȃG�l�I�������̏����^�[���ł��A��ɂȂ炸�Ɋ��ꂻ���ȋC�����Ă��܂��B �܂��A���̒��S���i�}�̐Ԋە��j�Ɏ��������邱�Ƃ��ł���͂��ł��B���n�|�C���g���ʒu�ɒ������邱�Ƃ��₳�����Ȃ�Ǝv���܂��B �u�Ђ˂�v�`�u���ǂ�v�܂ň�A�̓���œ�����悤�ɂȂ�̂ŁA��ւ��̃��Y�����r��邱�ƂȂ��A�^�[���̑O�������z�I�Ɍ}���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃł��傤�B �x�e�̊��o�́u���ʂ������Ă��鎞�v�B��������ƁA�o�����X����ɖ߂��Ȃ��痎������������̂Łu��Γ��v�Ǝv���Ă��܂��B ������Ɗϓ_��ς���Ƃ₳�����Ȃ�܂��ˁB���������������B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.26 ��{�Z�p 2006.7.21�ɓ��J�M�u���O�ŏЉ��Ă����u�r�`�i�@�A���y�����[�V���O�v���O�����R�@�`���h�����琬�ҁv�B ����͌��Ȃ���A�Ƃ������ƂŁA�X�L�[�W���[�i����������͂��܂����B �S�[���f���G�C�W�̎q�ǂ��������琬���鎞�ɒ��ӂ��鎖�A����́A�X�L�[�����łȂ��A�����̎�ڂ���ɂ������Ǝv���Ă���l�ɂƂ��ċ��ʂ̒m���ƂȂ��Ăق����B�̐S�̑�l�������A��ږ��̘A���ɕ��f����Ă��邱�Ƃ��C������B �q�ǂ��͂P�l�ł��낢��ȃX�|�[�c���o�����Ĉ���Ă����B �w�����鑤�̑�l�������A���Ă����Ă��邾�낤���H ���ʂł���m�������L�ł��Ă��邾�낤���H �����^�n��X�|�[�c�N���u��������j�ɁA���ʂ̂��������i�����܂ށj�ɓ`�B�E�[�ւ�}��˂E�E�E�E�B �Ő�[�̌������ʂy�����i����ɓ���Ȃ��ẮE�E�E�B �u�X�L�[�̊�{�v�Ƃ����B���Ȍ��t���A���낢��Ȑl�̃u���O�ɓo�ꂵ�Ă���B �u��{���ĉ����H�v�Ǝv���Ă���l�ɂ͎Q�l�ɂȂ���̂�����DVD���Ǝv���܂��B �q�ǂ��ɂƂ��Ắu��{�v�Ƃ́A��l�ɂƂ��Ă��u��{�v�ł��邱�ƂɁA�܂������Ȃ��I �w���҂͌��{�ƂȂ銊��������Ă����悤�I ������A�A���y���i�V���i���`�[���̌o��������u�i�V���i���f�����X�g���[�^�[�v�̗����̍s���E��������҂��Ă���B 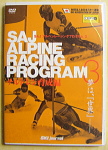 SAJ�@ALPINE�@RACING�@PROGRAM�@�R �`���h�����琬�� �\���E�ďC ���c�@�l�S���{�X�L�[�A���@���Z�{�� �A���y���� ���E��E�Ȋw�ψ��� �i�J�o�[�^�C�g���Ɂu�@���́w���E�x�E�E�E�@�v�Ƃ���܂����A����PROGRAM�S�ł́u�@���́w���E��x�E�E�E�@�v���K�ł��傤�B�j ����{���I�t�B�V�����u�b�N�̕t�^�Ƃ��Ĕ̔����Ă͂������ł���H |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.30 ����̗\�h �Б��ŋ��L�^�����������A�ӂ�����ɂł��܂����H 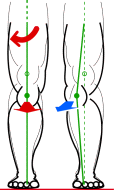 �̂̃o�����X�A���ɋr���̋ؓ��̃R�[�f�B�l�[�g�����܂��ł��邩�A�r���Ȃ������ɁA�G���^�������O�Ɉړ�����悤�ɋؓ�������B����̋�A�Ҋ߂̋�ɂ���āA�ӂ���Ă��܂��B �̂̔̓T�C�h�J�[�u����邭�A��ʐl�ɂ����ẮA�́E�r���̃o�����X�������Ă��A�A�u�̂̂Ԃ�v���u�X�L�[�̂Ԃ�v��U�����A���́u�Ԃ�v�ɂ��G�l���M�[�́u�X�L�[���Ԃ��v���ƂŊO�ɕ��o����A�̂ւ̕��S�͌y������Ă����A�ƍl���Ă���i�����̐搶�ǂȂ����⑫���Ă��������E�E�E�j�B �������A�����̃J�[�r���O�X�L�[�́A�X�L�[���[�̋Z�ʂ��킸�A�p�t���������Ă��܂��A�O�C�O�C��]���Ă��܂��悤�Ȉz���B�����āA���P����Ȃ��u�̂̂Ԃ�v�͂Ƃ����ƁA�u�X�L�[���Ԃ�v�Ȃ��Ȃ������߁A���̃G�l���M�[�́A�u�̂̒��ɂ��܂��Ă��܂��v�A�ƍl���Ă���B �Б����L�łӂ������A�G���^�������O�ɏo�Ȃ��āA�G��������O���̕����ɏo�Ă��܂��B ������A�x�тȂǂɕ��S��������A����ɂȂ����Ă��܂��B �u�G�l���M�[�v���u���ʁv�~�u���x�̂Q��v�A ������A�����X�s�[�h�����܂�ƁA�u���̂Q��v�ɔ�Ⴕ�āA�A�N�V�f���g�����������̃_���[�W�͑傫���E�E�E�B �i�{����Ȃ��ł���A�Q��ł���I�j Alpine Racing �̑I��͉ď�̃g���[�j���O�Ɋ��ɑg�ݍ��܂�Ă���͂��B ���͂���ȊO�̐l�B�ŁA������x�����Ŋ�������A�}�Ζʂ����邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă�����A�w����������A�v���C�Y���������A����Ȑl�B�B�{���B�w���҂��B �~��̃p�t�H�[�}���X���グ�邽�߂ɁA�����\�h���邽�߂ɁA���̉āA�����̑̂Ɖ�b���Ă݂悤�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.7.31 ��m���X�L�[��i���炿�ԂƂ����[���傤�j ������R�T�N�O�̂��ƁB�̎u���s������s�ֈ��z�����B�Y�z�̑ސE�Ґ��x�𗘗p���Ă̓]�E�̂悤���ƕ����Ă���B ���͓����S�T�B���̔N��ł̓]�E�͂���������ς������Ǝv���B ���͋�m��ƐΎ�삪��������O�p�B�����W��������̒��B�����ĉ䂪�Ƃ̎���͓c��ڂ��炯�B ��Ƃ����A���݁A�u�`���b�����A���e�B�[�N�R���N�V�����v�i���������W�߂����m�A���e�B�[�N�U�O�O�_���܂��W���j������s����ق́u��̍�v�B�������獪���{���Ɍ������Ă����ŃX�L�[�����Ă����B ��m��̑Ί݂ɂ́u��m���X�L�[��v������B�����̓��t�g���Ȃ��A�X�L�[���ł���悤�ɊJ������Ă����ΖʁB �u�s��v�Ɍf�ڂ��ꂽ�u�u�K�����v�ɎQ�������B���������Ă����Q���������B��ڂɂ́u�����ׂ�v���������B���i�����畃�ƕ��Ԃ��A�ƃ��N���N�������A���i���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�i�T�N���̎��ɍ��i���܂����B�j �����ď��߂āu�s���X�L�[���v�ɎQ�������B ���w�Z��w�N�́u�݂���E���v�B�����ʂ�R�[�X�r���݂̂�����E���̂��B ���w�N����́u�|�̃|�[���v�𗧂Ă��u��]���Z�v�B�m���X�g�b�v�E�H�b�`�łR�l���v�����ĕ��ς��o�����[���������ƋL�����Ă���B ���̃X�L�[���́A��������������ʼn^�c�����������B������͗��������p���������Ƃ��Ȃ��̂ɁA�傫�ȓ�Łu�؏`�v�i�Ԃ�����j����������������Ă��ꂽ�B���ł��L��������̂�����A�����C���p�N�g���������Ǝv���B �����ʼn���������A�ᔻ�������Đl�܂����ɂ�������Ƃ͈Ⴂ�A�����������Ă��F�Œm�b���o�������A���������ł������Ǝv���B��������a�̎v���o�ŏI��点�Ă͂����Ȃ��Ǝv���Ă���E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
���y�[�W�̐擪�� ���ŐV�̋L���� |
2006.8.2 �����s�X�L�[�A�� ���Z���ƌ�̐i�H�͓����������B�߂Ȃ����w�̖�ԕ��ɒʂ��Ă����B �����E��̐�y����A�u�V�����X�L�[�N���u����芈������̂ňꏏ�ɂ��Ȃ������H�v�Ƃ������U���������������B �P�X�W�O�N�̉Ă̂��Ƃ��B �E�������킩��Ȃ��ł������B���n�̃X�L�[��Ƃ����u�����v�A�u�c��v�͕��������Ƃ��������B �ʂ����āA�Ⴊ�~��̂��낤���H�����v���Ă����B���O�͂Q���B1���͑����Ă������A���낻��P�O�N�߂��ɂȂ��Ă����B �N���u�̕��ɐ�����ɘA��čs���Ă��炨���A�Ǝv���A������B �������āA�w�A�X�y���X�L�[�N���u�x�ɏ������A�����s�X�L�[�A���ɂ����b�ɂȂ邱�ƂɂȂ����B �����ē~���������A��̃~�X�^�[�X�L�[�i�E�A�����f����ڎw���Ă����w����ˊ�ہx���Əo��̂ł���B ���A�U��Ԃ�ƁA���̑傫�ȗ���́A�O�����Č��܂��Ă������̂悤�Ɏv���Ă���B �����s�X�L�[�A���ɂ����b�ɂȂ��č��N�łQ�V�N�B���ƂP���A�Q�N�撣��܂��E�E�E�B |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.3 ���q����쒓�Ԓn ���w���ɂȂ����B���s���]�˒��w�Z�ɒʂ����B �~��̑̈�̎��Ƃł̓X�L�[������w�Z�������B �w�Z���琔�S���[�g���Ύ����ʂɌ������ƁA���q����쒓�Ԓn������A���Ԓn�̒��ɏ��R������Ă��āA�����̕��X�����̏オ��X�L�[�œo�s�E���~�̌P�����s���Ă����B �̈�̎��Ƃ́A�P�T�ԕ��̎��Ǝ��Ԃ��܂Ƃ߂āA�ߑO���S�����X�L�[���Ƃɓ��Ă�A����Ȏ��Ԃ̎g���������A���q�����Ԓn�ɏo�|�����B �ፑ�ł͂��邪�A�S���X�L�[�̒B�l�ł���͂��͂Ȃ��A���S�҂ɂ͏��S�҂̗��K������A���܂������҂͂���ŏW�܂���K������B�������łɂP���������Ă������������������A�̈�̐搶�͂��܂������O���[�v�̃��[�_�[�Ɏ���C�����A���K�������߂�悤�Ɏw�����A���S�҃O���[�v�̖ʓ|�����ɍs���Ă��܂��B �o�b�a�e�X�g�̍u�K��ɖ��N�Q�����Ă������́A�v���[�N�{�[�Q���A�V���e���^�[���ŊO���̎g�����𒆐S�ɁA�u�K��Ŋw���̌��{������A�F�ŗ��K�����B �X�L�[�w���̏��̌��ł���B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.5 �}�e���A�� �S�O�N���X�L�[�����Ă���ƁA�X�L�[�����̔N�\�Ɍf�ڂ���Ă���X�L�[�̗��j�ɓo�ꂷ��X�L�[�̂قƂ�ǂ��A���̌��Ƃ��Ďg�p���Ă����B �P�i�A�W�A�X�L�[���J���_�n�[�̃r���f�B���O���S���C�q���҂݁F�A�w�O�j �� ���i�n�Z�K���X�L�[���X�e�b�v�C�����{����~�߂̃q���̃r���f�B���O���S���C�o�b�N���t�F���w�R�N��) �� ���w�S�N���̎��ɎD�y�I�����s�b�N������B �� �O���X�t�@�C�o�[�iHAGA�X�L�[���}�[�J�[�{����~�߂̃q���̃r���f�B���O���v���X�`�b�N�C�F���w�U�N���j ����̐��\���������ω��������ゾ�B ���ɃO���X�t�@�C�o�[�̃X�L�[�ɂȂ������A�s���X�L�[���łP�ʂƂ������ʂ������B �̂̐����ɍ��킹�āA���N�����ɔ����ւ��B ���̌�́A���Z���`�Љ�l�܂ŁA�u���U�[�h���g���Ă����E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.7 �V���e���^�[�� �n�̎��Ń^�[�����ւ��A�^�[���O���̑Ή����w�тȂ���A�p�������^�[���ւƓ����Ă����^�[���B ������芊��̂ŁA�F�X�Ȃ��Ƃ�������邱�Ƃ��ł���B ���̂̉�]���\���Ⴉ�����́A�X�L�[�����Ċp�t�����ւ�����@���Ƃ邱�Ƃ��A�B��A��B�ւ̋ߓ��ł������B �u�O���̊p�t�������߂ăY����U��������v�Ƃ����w���@���Ƃ��Ă���l������悤�����A���͌������B �����Ŋp�t�������߂Ăǂ�����̂��B���̂��߂ɑ�������ɏo�����̂��E�E�E�B �Ζʂ��ړ����Ă�����Ȃ̂ŁA�X�L�[�𑤕��i�J���j�։������炷�悤�ɓ���������ƁA�u�p�t���v����Ă��Ă��A�Y����̂��B �m���ɁA�傫�ȃn�̎����Ƃ�ƁA���ꂪ�����ɂȂ�A�p�t���ʂ��傫���Ȃ邩��A�Y���ɂ����ɂȂ�B �ł���A�����ȃn�̎��ł́A�������ł��傤�B �Ҋ߂̉����������A���ꂪ�O���Ɉʒu����B���̋��������L�[�v�����܂܁A�p�������^�[���̋O�Ղ̂���ɊO���ɃY��������̂��B ��Ȃ̂́A�^�[���O���ɏd�݂�`���邱�ƁB������܂����߂ɁB �d�݂����܂��`���A�X�L�[�̓Y����̂ł���B ���̈ʒu���A�O�X�L�[���O���Ɉʒu�������āA���S�͂���������X������A���傤�Ǘǂ��Ǝv���܂��H ����ɁA���p�Ƃ��āA�u�^�[���̑O���ŊO���̊p�t������邭���邱�Ɓv�����݂܂��B����͈Ղ����ł���Ǝv���܂��B ���̊��o���p�������^�[���̌㔼�����Ɋ����邱�Ƃ��ł��܂����H �u�p�t�������߂�v�A�u�p�t�������߂�v�A�u������܂��v�Ȃǂ��Ղ����g���[�j���O�������A ������u�V���e���^�[���v�ł���I ���ƂR�����ŁA�V�[�Y���C�����}����E�E�E�E�B�i�Ȃ������`�x�[�V�������オ���Ă��܂��H�H�j |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.8 �v���[�N�^�[�� �v���[�N�{�[�Q���Ŋ��邱�ƂɊ���Ă���ƁA�O�X�L�[�̊p�t�������܂��g����悤�ɂȂ��Ă���B �Y���ɂ�������芊���Ă����X�L�[���A�p�t���ɂ���ăY�������Ȃ��Ȃ�A�X�L�[�̊��������ǂ��Ȃ�B ����ƁA�p�t���ɂ���āA�O�X�L�[�ւ̓��������̔���p�Ƃ��āA�d�S���^�[���̓��������ֈړ����Ă���B ����ƁA���X�L�[�̊p�t���͂��ނ悤�ɂȂ�A�����݂̏�Ԃ��o�R���A�n�̎��̃|�W�V��������p�������^�[���̃|�W�V�����֕ω����Ă����B �v���[�N�{�[�Q������_�C���N�g�Ƀp�������^�[�����K�������悤�Ƃ�����@���B ���ꂪ�v���[�N�^�[�����I�Ƃ����s���|�C���g�Ȋ�����͖����A�u�v���[�N�{�[�Q���̏�Ԃ����ꂽ�v���̂���u�p�������^�[���ɂȂ��O�̏�ԁv�܂ŁA�ǂ�����v���[�N�^�[���ł���B�����v���Ă���B �b�͂���邪�A�w��������̎�ڐݒ���A�P���ȃv���[�N�^�[���ł͂Ȃ��A�u�v���[�N�{�[�Q������X�^�[�g���ăp�������^�[���ɔ��W����ߒ���\������A�W�J�̎�ځv�����͖]��ł���B�w���҂ƂȂ�ׂ��l�̗���́A�K�n�x���e�Ղɔ���ł���͂����B���ۂ̎w���̌���ł������Ɏg����Z�ʂ���Ǝv���B ���āA�����ŁA�v���[�N�^�[���̍\�����悭���Ă݂�ƁA�O���Œ�R���L���b�`���邽�߂ɑ���L���A�����֑�����ړ����邱�ƂŐ��܂�Ă���u�n�̎��v�A�ƁA�������O�X�L�[�̊������ɕ����ĊO�X�L�[�ɂ��Ă������Ƃ��邱�ƂŐ��܂�Ă���u��̎��v�̏�Ԃ�����B �u�n�̎��v�Ɓu��̎��v�Ƃ����A�V���e���^�[���̎��ɂ������錻�ہB �u�v���[�N�^�[���v�Ɓu�V���e���^�[���v�́A�Ƃ��Ɂu�n�̎��v�Ɓu��̎��v�Ŏ��Ă��邪�A�ʂ����ĉ����Ⴄ�̂��낤���E�E�E�E�B ���������̍l�@�ł����E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.10 �v���[�N�^�[���@���̂Q �u�v���[�N�^�[���v�Ɓu�V���e���^�[���v�́A�Ƃ��Ɂu�n�̎��v�Ɓu��̎��v�̃|�W�V�������\�ꎗ�Ă���B �ł��A���̂Q���r����ƁA����I�ɈႤ�_������B �w������������Ɏ��₵�Ă݂Ă��A�u�Y�o���v�̓������P�Ԗڂɂ͏o���Ă���Ȃ��B �^�[���̓�����ŁE�E�E�E�A�u��̎��v����u�n�̎��v�ɕω�����ɂ́A�X�L�[���������Ȃ��B �ǎ��ł̓������E�E�E�A�V���e���^�[���ł��������Ȃ��őǎ�肷�邱�Ƃ͏o����B ��Ɋ���~��āA�����猩�Ă���Ɨǂ��킩��B �����P�O���N�O�̎w�������C��ʼn����猩�Ă��ċC���t�����B ����̓^�[���̌㔼�ł���B �V���e���^�[���ł́A�O�X�L�[�̊p�t�����L�[�v�����܂ܐ�ւ����}����B ����ɑ��A�v���[�N�^�[���ł́A�p�������^�[���ɂȂ�悤�ɁA�u�j���[�g�����i���ɂ͎Ζʂɐ����ɗ��j�v�Ɉړ�����悤�ɊO�X�L�[�̊p�t�������߂Ă����B �Ō�܂Ŋp�t�����L�[�v����̂��A�r���ł��߂�̂��E�E�E�B �ǂ��̏�ʂ�����߂Ă����̂��E�E�E�B �^�[���i��邱�Ɓj�ɐ�������Ă͂����Ȃ��B �^�[���̓����ɋ�������Ɗp�t���͂��߂��Ȃ��@���@�����B �^�[���̓����ɓ|��Ă��܂�����̂��N�����A�̂�J���ֈړ��i�����j����̂��B �p�������^�[���Ŋ��肽���l�̓g���C���Ă��炢�����B �����������́A�X�s�[�h���ł�ƃt���[�Y���Ă��܂��p�t�����͂���Ȃ����Ƃ��A�u2006.5.25�v�ɔ��Ȃ��Ă��܂��B �����̎v���ƌ����̊���Ƃ̍��ɋC�Â��Ăق����B ���̓X�s�[�h���o�Ă��p�������^�[���Ŋ����Ă݂����E�E�E�B �v���[�N�^�[���Ŋ����ʂ��C���[�W���鎞�ɂ́A����o���̂P�^�[���ڂƂU�^�[���ڂł̓X�s�[�h���Ⴄ���Ƃ��ӎ����Ȃ���E�E�E�B �����āA�v���[�N�^�[���̗v�̂ŐF�X�ȎΓx�������Ăق����i�ɎΖʂ���}�Ζʂ܂ŁA�R������R�[�܂ł̒����������j�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.11 ���w�����{���u�K�� �Q�P�Q�Q�̂Q�V�[�Y���A���w������������Ă����B�W�R�N�W�S�N�̂��ƁB�������łɃT�����[�}���Ƃ��ē��{��傫�ȉ�Ђɋ߂Ă����̂ŁA�X�L�[�̓T���f�[�X�L�[���[�Ƃ��ēy�������S�ł������B �ɂ͗{���u�K��̎Q�����`���t�����Ă��āA�K��̎��ԎQ�����A�w���@�Ȃǂ��w�ԁB �K��̎��Ԃɂ͎��Z�̎��Ԃ����ł͑��肸�A���H���Ԃ��u�t�ƈꏏ�ɉ߂�������x�e�Ƃ��Ă��������Ȃ���~�[�e�B���O�������肷��B �u�����X�L�[�ɘA��Ă��āv�̉f��̍��̃X�L�[�u�[����肩�Ȃ�O�ł͂��邪�A���̔N��̎Q���҂̖w�ǂ͑�w���ŁA �P�W�l�ʂ����ǂ̒��ŃT�����[�}���������̂́A���Ƃ�����l���炢�������Ǝv���B ���ȏЉ�̘b���Ă���ƁA������w�́����X�L�[�T�[�N���ɏ������Ă��č��́~�~�X�L�[�X�N�[���ŃA�V�X �^���g�����Ă��܂��A�Ƃ��A�����X�L�[�w�Z�ɏ������Ă��܂��Ƃ��A�F�����`���A�Ɗ����Ă��܂����B �������A����Șb���Ă��u�����܂����v�Ƃ͎v�킸�A�u���������v�Ɓu�ł���v�͐����̊W�ł͂Ȃ��ȁA�Ƃ������Ƃ������Ă����B��������P���Ɂu�ł��Ȃ��v���u�ł���v�ɂȂ�Ηǂ��A�����v���Ă����B �ނ炪�����X�L�[��ɂ��ĂP�V�[�Y���i��P�O�O���j�����Ăł��邱�ƁA������R���łł���ɂ͂ǂ�������ǂ����A���邢�͂R��łł���ɂ́E�E�E�A�����s���ɖ߂��Ă��āA�������������l���Ă����B �u�ł��Ȃ��v�Ɓu�ł���v�̈Ⴂ���ώ@������A�l�@����B���̊���Ȃ����ԁA�����̃C���^�[�o������B�𑣂��Ă����B �����āA�T���͏�B���m�F���邽�߂̌���ꂽ���Ԃ�����A��ʂɗ����Ă��鎞�Ԃʂɂ������͂Ȃ������B �X�L�[�͐��ł�����̂����A��B�͊���Ȃ����ɂ�����̂ł���B �������Ċ��鎞�Ԃ�P���ɑ��₵�Ă����Ă��A���ꂾ���ŏ�B������̂ł͂Ȃ��B ���̉āA�Ⴂ�l�����́A���`�x�[�V�������グ�Ď��g��łق����B�����Ă��邱�Ƃ��A���̓~�A���邢�͂��̐�A�����Ǝ����ɕԂ��Ă��܂��B���؋���j����̃u���O�ŏЉ��Ă���悤�ɁA�P�x��P�������ɂ��Ă݂悤�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.12 �������x�X�L�[�� �����͑��ɋA�Ȃ��Ă���B�ߑO���Ɏq�ǂ������Ɛԕ��A�̎u���̏f���̏��֊���o���A���H�ɓ��̉w�u�̎u���`�����̓��v�Ɋ�����B �́A�̎u���w�̋߂��Ɂu������̉Ɓv�Ƃ����H��������A�����̖����Č������u������[�����v�������������B �����������[�����̃��X�g�ɂ܂���i�lj�����܂����B �H�����I��鍠�A�ׂ̃e�[�u���̐l�Ɗ�������킹�A�R�b��ɂ��݂��Ɂu�����I�v�Ƃ����V�[��������܂����B ���Z����Ƀu���X�o���h�œ����p�[�J�b�V������S�����Ă����P����̐�y�ŋ{�{����ɍĉ�A�Q�T�N�U��̍ĉ�ł��B �ƂĂ������������E�E�E�B �ߌ�͂������x�X�L�[��ցB �ď�́u�p�[�N�S���t��v�ɂȂ��Ă��܂��B�����͂X�z�[���~�S�R�[�X�����܂����B
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.19 �q�ǂ��̃X�|�[�c��w �Q�O�O�U�N�X���P�O���i���j�ɐV�������N�Â���E�X�|�[�c��Ȋw�Z���^�[�Ō��C��s����B �����e�@ �@�q�ǂ��̃X�|�[�c��w�@�`�������̉Ȋw�I�X�|�[�c�w���` ����| �@�q�ǂ��̐����E���B�ɉ������w���݂̍���ɂ��āA���̊�{�I�Ȏ����A�Ȋw�I�w�i�Ɋ�Â��A�X�|�[�c��Q���N�����ɂ����w���ɂ��Č��C����B�܂��A�X�|�[�c�����ɔ����h�{�⋋��X�|�[�c�h�����N�̑I�ѕ��ɂ��Ă��w�K����B �����̂�����́@�V�����X�|�[�c��Ȋw�Z���^�[�̃z�[���y�[�W�@���������������B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.22 �Ђ˂铮�� �J�[�r���O�X�L�[���o�ꂵ�āA�X�L�[����]���Ă����̂ŁA�r���Ђ˂铮�삪���Ȃ��čςށB �����̐l��������������B �{���ɂ������낤���H �X�L�[�̉�]���\���ǂ��Ȃ�A���삷��l���r���Ђ˂铮��Ń^�[�������[�h���Ȃ��Ă��ǂ��Ȃ�̂ŁA�^�[�����邱�Ƃ��y�ɂȂ����Ɗ����Ă��܂��̂��B �����̊��o�ƌ����͈�v���Ȃ����̂��B�X�L�[����]�����[�h���Ă��Ă��A��������Ƌr�͂Ђ˂��Ă���̂ł���B �����̈ӎ��Ɠ��삪�Ⴄ�P�[�X�Ƃ��Ă悭��������̂��A�X�L�[�̌����ȏ�ɑ�ڂ�����ɂЂ˂�A�G�ɑ������S���������Ă���P�[�X�B�G�͂Ђ˂邱�Ƃ��ł��Ȃ��߂̂͂��B �X�L�[�̉�]�Ƌr�̂Ђ˂肪�}�b�`����A���̗ǂ��Ђ˂�Ƃ́A�ǂ��������̂��낤���B �܂��A�X�g���X�����A�X���[�X�ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�u�ܐ�v�ł���B ���E�̊��o�����Ȃ����悤�ɁA�������Ă݂悤�B ���̓������ʂ����A��ڂ��Ђ˂�̂��B �Ҋ߂����^������ʂƁA�ܐ�̌������ς�镪�ʂ���������悤�ɁB ���́A�u��ڂ��牺���M�u�X�ŌŒ肳�ꂽ��ԁv���C���[�W���āA�Ҋ߂̋��^���������Ă���B ��������ƁA�v���[�N�{�[�Q���̃|�W�V�����ɂȂ��Ă��܂��̂��B �Ҋ߂̉��悪�������j�����N�I ����̊��o�̍����A���ɗ��R������ɂ́A�傫�ȍ��ɂȂ��Ă��܂��̂��B ���̐��ڎw���āA���A���𗬂����I |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.25 �㍻��x���ۃX�L�[�� �������x�X�L�[��̂���̎u���s�ƍ���s�̒��Ԃ��炢�Ɉʒu����X�L�[��B ���Ɉڂ�Z��ł���N�ɐ���s���悤�ɂȂ�B�o�X�����p���s���̂������B �㍻��̃X�L�[��́A�[�ɎO�p�����̃��b�W�i�x�e�����H���j������A���ɂ��莝�Q�{���[��������Ԃ������B ����ɂ��Ă��A�k�C���̃X�L�[��̃��[�����͖{�i�I�Ȃ��̂������A�u�n�Y���v�ɏo������L�����Ȃ��قǁB �X�L�[��Ƃ����ǂ�����Ȃ��E�E�E�B �m���A���Z�P�N�̍��ł������Ǝv���B ���t�g�����p����Q���t�g�̋}�Ζʂ����낤�Ƃ��Ă������A���t�g����t�߂ő�l���U�E�V�l�W�܂�A�V���e���^�[������K���Ă�����i�ɑ�������B ��Q���t�g�𐔖{�����Ă������A��l�����͂܂������Ƃ���œ����悤�Ȃ��Ƃ����Ă����B �M���w�������Ă���l�������B �M�S�ɃV���e���^�[������K���Ă����B �i�ǂ����āH�H�j �i�������l���Đ��N���o�����Ƃ��A�X�L�[�G���Ɍ��f���̍�����O����̉�ژ^���f�ڂ���Ă����B�ǂ������̎��̃V���e���W�c�́u���{�X�Ɂv�ƌĂ�Ă������X�̂悤�ŁA�f���I�̗��K�����Ă���l�����������̂ł���B�j ���̌�A���a�T�T�N�R���A��P���b�X�L�[�I�茠���A��a���X�c�X�L�[��ōs��ꂽ�B �u�D�������n���g�c�K��I��v�Ƃ����^�C�g���ŁA�[���̃e���r�j���[�X�����Ă��ċ��R�m��̂ł���B �����֏o������P�T�ԑO�̂��Ƃ������B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.26 �X�L�[���� �����͐V�������Ē��������������֍s���Ă��܂����B��������ό��Ԃǂ������J���ł��B ��������Ƃ͎d���̂��t�������̑��A�X�L�[�����ꏏ�����肵�Ă��܂����B�i���v�ȂƂ��j �~�͂Ԃǂ������N���[�Y����܂��̂ŁA�V�[�Y�������w������X�L�[���y����ł����܂��B ���������āA����芊�������͑��������H�H
�V�����k�����S���Ē���{�� ���n�h�b����P�ڂ̐M�����E�܂��Ă����I�I |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.27 �V�������ߑ���p��  �����͒����s�ցB �����͒����s�ցB�V���P�T������J�Â���Ă����u�E�B�[�����p�A�J�f�~�[���i�W�i���[���b�p�G��̂S�O�O�N�j�v���ӏ܂��Ă��܂����B����Ƌx�݂̒������o���č����ƂȂ�܂����B �i�O�������ݐ��Ђ����ōw���B���肪�Ƃ����{����B�j �����͈���Q���Ԕ��B���p�ӏ܂ɂ͏W���͂Ƒ̗͂��v��܂��B �X���P�O���܂ŊJ�Â���Ă��܂��B �Q�O�O�U�N�̓��[�c�A���g���a�Q�T�O�N�̋L�O�C���[�ł��B���ɂ��|�X�^�[���f������Ă��܂����B http://www.mozart2006.com/ �I�[�X�g���A�͎R���X�����������ς��ł��ˁBWC���[�X�����ƂQ�����Ŏn�܂�܂����E�E�E�B �V�������ߑ���p�� �V���������s�{�֒������|�Q�V�W�|�P�S�@�@TEL 0258-28-4111 �����s�܂ōs�����̂ŁA���ׂ�̋����s�܂ő���L�����H�B �ړI�n�́u����������v�ł����B
�V���������s����P�T�S�T�|�P TEL 025-799-2056�@�@��x���F���j���@�@�c�Ǝ��ԁF�P�P�F�O�O�`�P�S�F�S�T�@�@�P�U�F�O�O�`�P�X�F�O�O |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.8.31 �R�b�v�̐� ���̐́A���R�ŕ������b�ł��B �����̓��͎��̓R�b�v�Ȃ̂ł��B ���܂ł̒m���ƌo���Ő������X�ƈ�t�ɂȂ��Ă���̂ł��B  �V�����m���ƌo�������̃R�b�v�ɓ����ɂ͂ǂ�������ǂ��ł����H �V�������𒍂��ɂ́A�R�b�v����ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B �R�b�v�̐����̂Ă܂��B �ƕ����܂������A���͂��������Ȃ��̂ŁA���݊����܂��B ���݊����ƁA�̂̒��ɐ��ݓn��܂��B �����āA����ۂɂ����R�b�v�������o�������A�V��������������܂��B �ǂ�ȂɗL���ȃX�L�[���[�̘b���Ă��A�ƂĂ��f���炵�����b�X�����Ă��A�葤�̊�ɐV������������������Ȃ���A���Ԃʂɂ��Ă���ƌ�����̂ł��B ���l�i�ЂƁj�̘b������A�u���O��{�ŕ��͂�ǂގ��́A�����̃R�b�v����ɂ��Ă��܂��B �܂��A���̘b�Ƃ͑���̔N��ɂ͊W����܂���B�N��̐l��������A�N���̐l��������E�E�E�B ������A���ȊO�̐l�́A�F�A���̐搶���Ǝv���Ă���̂ł��B �Ƃ͌����A���̃R�b�v�ɂ́A�ǂ����r�[����������Ă���悤�ł��E�E�E�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
���y�[�W�̐擪�� ���ŐV�̋L���� |
2006.9.7 �ؓ��� ���w���������i���A���w���������Ă������i�P�X�W�T�N�`�P�X�W�V�N�j�A��z�V�����͂܂����w���n���ł������A���̐V�������X�L�[�̏�B�������Ă��ꂽ�B �����̓��{��傫�ȉ�Ђ́A�y�j�����ߑO���܂ł̉c�Ɓi�����锼�h���j�ŁA�P�Q���`�P�R���̏�씭�ɏ��ƁA�P�T���ɂ͐ΑŌ�y���X�L�[��̎R���ɓ������邱�Ƃ��o�����B ��������ĂP�Q���̉��{���疈�T�ʂ������A�R�����ɂȂ�ƁA�R���֓����͂�����̂́A�u����C�́v���ނ�����A�̂��v���悤�ɓ����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ��A�����������B ���̌�́A�P�P���ɃI�[�v������X�L�[��֏o�|������A���̂����A�u�ꍂ���ł��V�R��ŃI�[�v�����邱�Ƃ͋H�ŁA�l�H��̃X�L�[��ŃV�[�Y���C�����}����悤�ɂȂ�A�d����ő̂ւ̕��S�����܂��Ă���ƁA�������߂������ɂ́A�̂��v���悤�ɓ����Ȃ��Ȃ��Ă����B �R�O�Α㔼�ɂȂ��Ă������Ƃ������Ǝv���Ă������A�����ł��Ȃ������B ���w�Z�̐搶�Ńo�X�P�b�g�{�[���ē̕P�H����A�u�v���e�C���v���Љ�ꂽ�B �P�X�W�T�N���̃v���e�C���́A�����S���ŁA���⋍���ɂ��n�����炭�A�ʂɂȂ����肵�Ă����B �Ƃ��낪�A�u�o�j�����v��u���[�O���g���v�Ȃǂ�����A�V�F�[�J�[�ŗn���Ƌʂɂ��Ȃ炸�A�ƂĂ����݂₷�����̂Ƀv���e�C�����i�����Ă����B �ڕW�������ăX�L�[�Ɏ��g��ł���T�����[�}���̏��N�I ���T�X�L�[�ɏo�|���Ă��邠�Ȃ��I �ؓ��ɂɃV�b�v��Ȃǂ��g���Ă���ꍇ�ł͂Ȃ��B �X�s�[�h���o���Ċ�������A�}�Ζʂ��������肵�Ă���Ƃ������Ƃ́A�r�E�w�E���ȂǁA�S�g�̋ؓ��ɁA�q��łȂ����ׂ��������Ă���̂��B���\�L��������o�[�x�������ɒS���A�X�N���b�g�����Ă���悤�Ȃ��̂��B�������āA�ׂ����ؑ@�ۂ��f�Ēɂ݂₾�邳�������N�����Ă���̂ł���B  ����ς����𑽂��ۂ�@���@�^������Ƀv���e�C���@���I�X�X���������B ���͕����ł��A�ؓ��ɂ��c���Ă���ꍇ�́A���ӂ̐H���O�ɐۂ�悤�ɂ��Ă���B �ʐ^�́A2000�N��舤�p���Ă���R���[�Q������uZAVAS PROTEIN XX LBM�v�B �i�������ɂ͎��Q���Ă��܂��j ���i�̏ڍׂ� �������ي�����Ђ̃z�[���y�[�W ���I �ΑŌ�y���X�L�[��i���F���q������y���X�L�[��j�ɂ��Ẳ�ڂ͌�قǁB |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.8 ���������X�L�[�� ���ł����P�Q������R���܂Ŗ����Q��͖K���X�L�[��ł��邪�A���߂ĖK�ꂽ�̂́A�P�X�W�V�N�̎w�������������B �����̏��w���������́A���̐����Ǝu�ꍂ���T���o���[�X�L�[��̂Q���ŊJ�Â���Ă������A���̓T���o���[���ł̎ł��������ƂƁA���i��̎w�������C��͐��P�Q���̎ԎR�����X�L�[��ŊJ�Â�����ɎQ�����Ă����̂ŁA�w��������܂ŁA�����ւ͍s�������Ƃ��Ȃ������B ���̔N�A�A�X�y���X�L�[�N���u����̎Q���͎������ŁA�E�������킩��Ȃ������̂ŁA�����{���h�ɂƂȂ��Ă����u�z�e����܂т��v�Ƀn�K�L�ŏh����\�����B�����͓��������s�o�X�𗘗p�����B �z�e���̔z���ŁA�����s�̎҂R���̑������ł������B��肳��A��������A�Ǝ��B ���߂Ă̏o��ł������̂����A���N��A�Ȃ�Ɠs�A���畔�̐��ψ��Ƃ��ĂR�l���ĉ���̂ł���B �s�v�c�ȏo��ɁA�ƂĂ��������B �Q���Җ��낪�c���Ă��Ȃ��̂ŁA�����O�͎��O���Ă��邪�A���̎��̔Ԃ̕�����A�S��ڂ��I�������Ɂu�ƂĂ���肭�āA�v���b�V���[�ɂȂ�܂����I�v�ƖJ�߂�ꂽ���Ƃɂ��������B�A�����Ă���킩�����̂����A���쌧�̑�\�I��̃E�G�A��g�ɂ����Ă������ł������B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.10 �q�ǂ��̃X�|�[�c��w���C�� �����A�V�������N�Â���E�X�|�[�c��Ȋw�Z���^�[�ŊJ�Â��ꂽ���C��́A�Q���Ԃł͊w�т���Ȃ����e�ł������B �V����w�㎕�w�����a�@�����ȁ@��t�@�c�����������u�t�ɂ��}�����A�X�|�[�c�w�����E���t�E�h�{�m���R���ÂP�O�O�����̕��X�ƂƂ��ɔq�������B �q�ǂ��̐����ƃX�|�[�c���l���鎞�A�h�{��ۂ�̂����Ƃ����v�f���K���K�v�ł���B �u�H�ׂ邱�Ƃ��g���[�j���O�ŁA�H�̃R�[�`�͕�e�B�ł����Ăق����E�E�E�v�Ƃ̃R�����g�B �W���j�A�A�X���[�g�ɂ͓��R�K�v�ł��邪�A�]�̔��B��w�͂̌���ɂ��W���邱�Ƃ����ɁA���ʂ̂�������₨����ɂ��m���Ă��炢�������e�B ���̂�����́A�����Ȋw�Ȃƌ����J���Ȃ��^�b�O��g��ŁA���w�Z�⒆�w�Z�̉Ȗڂ̈�Ƃ��Ď��g�݁A��l�ɂȂ邽�߂ɕK�v�Ȓm���Ƃ��Ċw���邱�Ƃ�APTA�����ւ̏����Ȃǂ���A�q�ǂ�����Ă邽�߂̒m���ƕ��@�_�̌[�ցA���y�ɂƂ߂Ȃ��ƁA���S�ȑ̂ƐS���������Ȃ��B �����Ȕƍ߂���������Ă��鍡�A��������͂��߂Ȃ��ƁA�T�O�N��ɂ͂Ƃ�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B IT�Z�p�ɒ������ꕔ�̐l�������E���̂ł͂Ȃ��A�N����������������ɂ��T���Ȑl��������������̂ł͂Ȃ��A���ʂ̂�������₨����ɓ͂����@�i�V�X�e���j����邱�Ƃ��A���ł��n���ł��A��l�����̐���̂��߂Ɏ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł���A�Ǝv���Ă���B�F�X�Ȑl�����Ƃ��̘b�����Ă݂悤�B ��w�Ƃ����ϓ_�͒m��Ȃ�����ł��������A�X�|�[�c�����ɂ͕K�v�Ȃ��Ƃ̈ꕔ���A�Ƃ̔F���͂������B �E�X�|�[�c���Q�͐l�ЁI �E�I�[�o�[���[�X�A�I�[�o�[�g���[�j���O�A �E�^���ƚb���A �E�S���kṁi��������Ƃ��j�A�ˑR���AAED�A �Ƃ������e�̂��b���A �X�L�[�������ɁA���ɂ������ǏQ���҂Ɍ��ꂽ���A�u�t�Ƃ��Ăǂ��܂ʼn����ł���̂��B �u�t�A�p�g���[���ƃX�L�[��̑Ή��A�~���~�}�Ƃ̘A�g�A��������G���A�A��������G���A�̏��C�Ȃ��Ă���B ���Ȃ�ȑO����A��������X�L�[��̑�\�d�b�ԍ���A�p�g���[�������̒��ʓd�b�ԍ��͌g�ѓd�b�̃A�h���X���ɋL�^���A�u�K����������ۂɂ͌g�ѓd�b���|�P�b�g�ɓ���Ă���Ƃ���ł͂��邪�A�v���Ȓʕ�͂������̂��ƁA�~�}������������܂ł̊ԁA�����ł��āA�������Ă͂����Ȃ��̂��A�V�[�Y���ɓ���܂łɁA������x�������Ă݂悤�Ǝv���B ���@AED �mAutomated External Defibrillator�n�@�ˑR�C�S��~��ԂɊׂ����Ƃ��ɑ������ėp����~�����u�B ����V������Љ�ʂɌf�ڂ���Ă����L�����Љ�����Ǝv���܂��B �y�Q�l�T�C�g�z �����킢FC�����T�C�g�FJFA�n���h�u�b�N��U6�AU8-10�̃n���h�u�b�N�ȂǁAPDF�t�@�C�������邱�Ƃ��ł��܂��B �����X�|�[�c�Ȋw�Z���^�[�F�R����/��Ȋw�_�d/�c���f�q����̉h�{�ɂ��镶�����Q�l�ɂȂ�܂����B �A�X���[�g�̂킢�킢���V�s�F�����X�|�[�c�Ȋw�Z���^�[�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B �H���o�����X�K�C�h�F�C���X�g�����p����킩��₷�����e�B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.14 �o�� �o�����邱�Ƃ��ėǂ����Ƃł����H ��肭���肽���A�v�����Ƃ���Ɋ��肽���A�X�L�[���[�Ȃ�N�ł������v���͂��B �����͂ǂ��ł��傤���H �v���Ԃ�ɂ�������犊��̎����K�����ƕς���Ă���A�Ƃ����l�����܂����A�S���ς���Ă��Ȃ��l�����܂��B ���W���[�X�L�[���[�������A�ڕW�������Ď��g��ł���l���ꂼ��Ɂu��肭���肽���A�v�����Ƃ���Ɋ��肽���v�Ǝv���Ă��āA���̎v���ʂ�ɒB���ł��Ă���l�ƁA�ł��Ă��Ȃ��l���łĂ���B �ʂ����Ă��̍��͉��H�H �ŋߎv���̂ł����A�o���ɂ́u�v���X�̌o���v�Ɓu�}�C�i�X�̌o���v������̂ł͂Ȃ����낤���ƁB �u�v���X�̌o���v�F���܂��ł������Ƃ��o�����邱�ƁB �u�}�C�i�X�̌o���v�F���܂��ł��Ȃ����Ƃ��o�����邱�ƁB �u�v���X�̌o���v���ǂ�ǂ�~�ς��Ă����Čv��ǂ���ɏ�B����l�ƁA�u�}�C�i�X�̌o���i���̎��̊��o�j�v���㐶�厖�ɒ~�ς��Ă��܂��A�u���܂��ł���v���Ȃ��Ȃ��o���ł��Ȃ��l�B �u�}�C�i�X�̌o���v���u�v���X�̌o���v�ɕς���ɂ́A�v�l���K�v�ł���B �̂�ڕW�ǂ���ɓ��������݁i�V�~�����[�V�����j���K�v�ł���B ���̍�Ƃ͊����Ă��鎞�ɂ͂ł��Ȃ��B���K�͗��K�̎��Ԃɂ����ł��Ȃ��B �v�l���鎞�Ԃ̗ʂƁA�����̑̂��q�ϓI�ɒ��߂Č����Ǝ��Ԃ��m�ۂ������Ƃ���ł���B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.16 �����~ �����Ƃ�Ƃ����������܂���ˁA�����~����K���Ă���l�B �����~�Ȃ�Ă������o���܂���A�Ȃ̂ł����A���̍������̂͂ł��܂����H �����Œ����~�����Ȃ���A���L�^����������ǂ��Ȃ�܂����H �A�i���O�̏d�v�̏�ŋ��L�^����������A�j�͂ǂ������ł��傤���H �����ʒu����r���Ȃ���u�ԁA�Ⴂ�ʒu���痧���オ�������A���Ȃ��̑̏d�̓_�C�G�b�g�ɐ������܂��B �X�L�[���ʂɉ��������Ă������ł��A�����Ă��܂��B �X�L�[���ʂɉ��������邽�߁A�͂��������邱�Ƃ��K�v�ł��B�����̈ӎ��ƁA���R�̖@������v����Ƃ͌���܂���B �L���ɎΖʂŕБ��̒����~�����Ă݂Ă��������B ����ɁA�Б������~�����Ȃ�����L�^�������Ă݂Ă��������B �ӂ�ӂ炷��l�́A�R���ɂȂ��Ă��܂��͂��B �^�[���^���̒��ł��A�p�������^�[�������Ă��鎞�̐�ւ��̏�ʂł́A�Ζʂ��ߕ����ɒ����~����悤�ȃo�����X��K�v�Ƃ���ǖʂ�����͂��ł��B ����Ȋ����ŁA���N�u�O�v�ɖ߂�悤�ɂ��Ă��܂��B���V�[�Y���ɐF�X�w���Ƃ܂��A��Ԃ₳������ʂ���A�����̊����g�ݗ��Ă�A�l��������Ƃ̒��ōs������A��̏�Ŋm�F�����肵�Ă��܂��B �������߂��Ƃ́A�₳�������Ƃ���n�߂�Ɍ���܂��B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.18 �R��� ���w���������i���Ă��A�����ɑ���Ȃ����̂��z���������Ǝv���A���C�R�X�L�[��ɂđ啽���N�f���̍u�K��ɎQ�������̂́A�W�T�N�P���Ǝv���B ���̎��̈�Ԃ̉ۑ�ƂȂ����̂́A�w�R���x�B ���f�B�E�X�̐��l���傫�������̃X�L�[�ŁA�ɍׂ��V���v�[����`�����Ƃ���B �Ƃɂ����u�����I�v�Ƃ��Ă���̂��B�̂̃o�����X�������ƁA�V���v�[�����Ԃ��B ���ꂩ�疈�T���̃g���[�j���O�́A�������ΑŌ�y���X�L�[��ł���B ���̍��͂P���P�R���Ԃ��炢�Q�����f�ɂ����B���H�𑁂߂ɒ����A�W���߂��ɂ̓Q�����f�ɏo�Ă����B �������A�����̓V���O�����t�g�����Ȃ��A�P�O�����߂��鍠�ɂ́A�ǂ̃��t�g����ɂ��s�ł���B �����Ȃ�ƁA�v�����悤�ȃg���[�j���O���ł��Ȃ��Ȃ�̂ŁA�u���X�g���� �C�C�z�[�v�̉��i�P�W�ԃz�[���̃t�F�A�E�G�C�j������̊ɎΖʂŁw�R���x�Ɏ��g��ł����B�i���̑O�̔N�́w�߃v���[�N�x�̎������߂�g���[�j���O�ł����B�j ���̃V�[�Y���́A�w�R���x�̗��K�ɂ��Ȃ�̎��ԂĂ��B ��]���a�͂߂��Ⴍ����傫�����A�̂̔ŃJ�[�r���O�^�[�����ł���܂łɂȂ��Ă����B ��x�u�ł���v�Ƃ����o��������ƁA�u���ł��ł���v�Ƃ����̂͊���Ƌ߂��Ƃ���ɂ���A�e�ՂɎ�ɓ���邱�Ƃ��ł���B ���̂��߂ɂ́A���_���}���ł͂����Ȃ��B ��������ƖڕW�Ɍ����Ď��g��łق����B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.20 �����}�I�肯�������͗l�ł��i�ƂĂ��S�z�E�E�E�j ���W�r��̃X�L�[���[���������Ă��鐯���}�I��A�Q�[�g�g���[�j���O���ɉ��䂵���݂����ł��B�S�z�ł��E�E�E�B ���E�łP�O�Ԉȓ��ɓ��邱�Ƃ��o����\�͂�����ޏ��̂��Ƃł�����A�̗͓I�ɂ����_�I�ɂ��A�����������傫���Ȃ��Ăق����E�E�E�B������Ȃ��Ă�������ł��E�E�E�B���͓����Ȃ��Ă��B �������Ă��܂��E�E�E�B �����}�t�@�� |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.23 �X�|�[�c�z�e�����h�t �Q�O��O���ɃX�L�[�ɔM�������ʂ������邱�Ƃ��ł����̂́A�X�|�[�c�z�e�����h�t�̎В��u����ˊ얾����v�Ƃ̏o����S�Ăł���B�i���݂��ό��J���X�}�Ƃ��Ă�Ă���A�O���[���c�[���Y���R�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ��ĐV�����S�̂̊����ɂ�������Ă���B�j ���{�l���f�����X�g���[�^�[�I�l��ɏo�ꂵ�Ă����I��ŁA���i�V���i���f���́u����ˊ�ۂ���v�͒킳��ł���B �X�L�[�Z�p�̘b�͈���Ȃ��B�������A���g�ݕ��A�l�����A����_�A�ǂ���傫�ȉe�������B�u�����̃X�L�[���������v�Ƃ��������ɂ��ẮA���̋����͖��N���肳�ꑱ���A�������g�ݑ����Ă���Ƃ���ł���B ��z�V�������J�ʂ��Ă���́A�V�����Ŕ�������Ă������̑����A�u�g�������������Z���Ă���������v�Ɨa���Ă�������A���̑���������߁A�ΑŌ�y���X�L�[��֒ʂ��Ă����B �y�j���̒��߂��ɓ������o�����A�P�T���߂��ɂ͐ΑŌ�y���X�L�[��̎R���ɗ����Ă����B�����āA���X�Ɨ��K���A���j���̌ߌ������A�i�C�^�[�܂Ŋ���悤�ɂȂ��Ă����B���j�̒��A�В��v�l�̖��q����͒��H�Ɂu���Ɛ������Y�R�V�q�J���P�O�O���̂��ɂ���v��p�ӂ��Ă�������A����w�܂ő����Ă������������B�����A�V���̎��Ƃ��瓌���֒ʂ��Ă���A����Ȋ��o�ɂ��Ȃ��Ă����B �X�L�[�̓���̓z�e���ɗa�����Ă����������̂ŁA�X�[�c�ɃR�[�g�A�v�C�̃r�W�l�X�}�����ፑ���������Ă����B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.26 ���x��Љ� �P�X�V�O�N��㔼�Ɂu���x��Љ�v��������������ė���A���������Ă����B ���w�����獂�Z�����������́A���̂悤�ɍl�����B �i�P�j ��`��鑬�x��������ƁA���{���ǂ��ɂ��Ă��ς��Ȃ��Ȃ邼�B�s��Ɠc�ɂ̍����Ȃ��Ȃ邼�B���ԂƋ�Ԃ̍����Ȃ��Ȃ邼�B �i�Q�j ���ԂƋ�Ԃ̍����Ȃ��Ȃ�ƁA�y�n�����邱�Ƃ̉��l����������A�y�n����R����k�C���͂���܂ňȏ�ɖ��͂���Y�Ɗ������W�J����邾�낤�B �i�R�j ���ԂƋ�Ԃ̍����Ȃ��Ȃ�ƁA�ǂ��ɂ��邩�͖��ł͂Ȃ��A�����������l���s�����Ă��������d�v�ɂȂ邾�낤�A�ƁB �Q�O�O�U�N���݁A�i�P�j�Ɓi�R�j�͂����悻��������Ă���Ǝv���B�i�Q�j�͂܂��Ȃ̂�������Ȃ��B ���Ɂi�R�j�̂��Ƃ���A���Z�𑲋Ƃ�����㋞���A���{�̒��S�ɗ����Ă݂āA���A���{�ʼn����s���Ă��āA������������ǂ��v�����A���������邩�A���ȏ��ɂ͏����Ă��Ȃ�����������A�����Đ����ł�����k�C���ɖ߂�̋��̂��߂Ɋ撣�낤�A����Ȏ����l���Ă����B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.28 ���{��傫�ȉ�� �����œ������ƂɂȂ����B�P�O�N�Ԃ����ĉ����������悤�Ǝv���Ă����B�P�O�N�撣���āA���̎��̂P�O�N�Ԃ̖ڕW�����߂悤�Ƃ��v���Ă����B �N���ƕی��̎d���ɏA�����B����J�����̑O�̃r����A��W�����ƈ�̓��ʂ�̌����_�߂��ł�������A�O��̓d�M�d�b�̉�Ѓr�����Ζ��n�ł������B ���ƃv���W�F�N�g�̎d���������B���{��傫�ȉ�c��ɏo���肵����A�N���ɂ͗��N�̗\�Z�����߂邽�߂ɒ��܂œ������肵���B�X�L�[�ɂ��M���������A�d�����D���������B �ڕW�̂P�O�N�ڂ��������悤�Ƃ������A���肵�����������̂Ă邱�Ƃɂ����B ��������ɓ���Ă��A�s����ېg�ɑ���l�B�̎p��ڂ̓�����ɂ��Ă������ƁA�V�l�ɂȂ�������ɂ͓V����̃V�X�e������̂����ł��낤���ƁA���̓�������ɐi��ł������Ƃ��Ɏ��ӂ����e���������̑̂ɂ͓��ꂽ���Ȃ��������ƁA���ɂ���A�u�s���͌������v�B �ǂ�������_�ɍ����|����ƁA�y�ȕ��̓��ł͂Ȃ�������̓���I�����Ă��܂��B �g�D���痣��Čl�Ƃ��ĉ����ł��邩�A���������āA�����ĘV�l�ɂȂ邱��ɂ͌������Ȃǂ��ւ邱�ƂȂ��A���邭�y���������Ă������E�E�E�B ����ɂ��Ă��A�����ꏏ�Ɏd�������Ă�����y���X���A�e���r�̒��œ��������Ă���p������̂͂ƂĂ��h���B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.29 �q�ǂ� ���w���������Ă������A�A�X�y���X�L�[�N���u�œ��������Ă����P�O�ΔN��̎O�c������ɂƂĂ������b�ɂȂ����B ��茧�o�g�̕��ŁA���Ƃւ����ז����Ă����b�ɂȂ������Ƃ�����B��ԃf�U�C�i�[�Ƃ��Ċ���Ă��āA���c��ߕӃX�L�[��̃z�e����^�X�L�[��R�[�X�̐v�Ȃǎ��т�����A�v�r���̖͌^�Ȃǂ������Ă����������B �X�L�[�ւ̏�M�͂ƂĂ��傫���A�ނ��Ⴂ���Ƀg�b�v�f�����������c�F�j����̂P�U�~���t�B�����������Ă����������B ���ژA�������A�X�L�[�w�����{�̏��Ŗ{�̎B�e���I����Ď��̎B�e�̍��ԂɎB�e�����Ă����������A�Ƃ����M�d�ȉf���ł������B �ނ͂R�l�̎q��Ɍb�܂�Ă����B�����ĂR�l��������A�Ƃ����b���f�����B ��e�̎�͂Q�{�����Ȃ��A����Ȃ��̂ɁA�R�l���Ǝq�ǂ��Ȃ��烋�[�������܂���A�Ƃ������ƁB �����āA���Ȃ�ɍl�������ƁA ��l���q���i�T�j�A���B�i�����𒆐S�ɍl����̌��j ��l���i�x�����j�A���Ƃ��Ȃ��B�i�Η�����̌��j �O�l���i�v���j�A�������B�i�b�Ƃ�����ʂ��璇�ԂƂ����ӎ���̌��j ���{��傫�ȉ�ЂłP�O�N�ڂ��}���邱��ɂ́A�Q���R����������R���S����������A���̕��̒��ւ������ɋl�߂ďo�Ђ��閈���ł������B���̍��ɂ͂Q�l�̎q��Ɍb�܂�Ă������A������l�~�����ƁA�^���ɍl���Ă����B �������P�S�̍��A�q�ǂ��Ȃ���ɐF�X�l���Y�ގ��A���e�Ɉӌ��������Ƃ��������B �Z�����āA���w���ɂȂ�q�ǂ������e�Ƃ��Ă͂Q��ڂ�������Ȃ����ǁA�Q�l�ڂ̎q�ǂ������w���ɂȂ�̂͏��߂Ă̑̌��ł���I �������g�̕���_���}���鍠�A�Ƒ��ɂƂ��āA�����ɂƂ��Ă̍œK�ȁu���v���������������B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
2006.9.30 �ő���� �œK�ȁu���v�����߂邽�߂ɏ����W�ɂƂ߂��B �����Đi�H���u�V�����v�ɂƂ����B �k�C���ɍs�����`���߂��ɂ���B �����ɍs�����Ǝv������V�����œ��A�肪�ł���B �ǂɂԂ��������ɂ�������z����p���X�L�[����w���Ƃ܂Łu���v�ɂ��邱�Ƃɂ́u�E�C�v���Ȃ������B �d���̓X�L�[�E�G�A�̌������ɋΖ����邱�ƂɂȂ����B�V���l�̒n���s�s�ŒN��l�Ƃ��Ēm��l�͂��Ȃ��A����Ȋ��ł������B�܂��C���^�[�l�b�g�͖�������ł���B�߂��ɃX�L�[�ꂪ���邱�Ƃ͓��H�}�b�v�Œm�����B�i��ɂ��̃X�L�[�w�Z�̕��X���g�����}���Ă������������Ƃ����̎������x���Ă���B���ӁI�j �X�L�[�A���̃i�V���i���`�[���̃E�G�A����ЂŐ������ɂȂ�������i�P�X�X�Q�N�j�A�o�Ђ̃E�G�A�ɂ͂ƂĂ��������B �u�ނ���߁v�Ƃ������ŁA�����E�G�A�Ȃ̂Ɉ�l��l�����ɈႤ�̂��B ����Ȃ̌������ƂȂ������B �V�������Ƀ`�������W�����Ƃł���Ɖf�����B ����Ȑl�����ƈꏏ�Ɏd�����ł�����Ǝv���A������������B �����̓����{�Ђ̉�͐�O�́u���ÔZ�v�ɋ߂��Ă��āA�����s�̃X�L�[�N���u�ɏ�������A�ԏ鍂���ւ̃X�L�[�s�ɔM������Ă����������B�����Œ��J��t����e�q�Əo��̂ł���B�����Đ����������J��t������X�^�[�����̉�Ɉ������킹�A�����J���w�̂���������z������A�u�ꍂ���̊J���Ɍg�������ƁA�X�L�[�E�̔��W�ɑ���ȍv�������ꂽ���ł���B�ڂ����͓��{�o�ϐV���̘A�ڃR�����Ɍf�ڂ��ꂽ���e���������������B ����ȕ��X�ƈꏏ�ɏ�C�֏o���ɍs�������Ƃ��������B�����ĂW�N�ڂɉ�Ђ����錈�ӂ�����̂ł���B �ʖڂȂ��̂͂��߂ŁA�����Ȃ��̂͋����Ȃ��̂ł���B �����Ă܂��������I�����Ă��܂��̂ł������B |
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||